「おい氷室、ちょっと話がある」
翌朝登校してきた修也は、自分の席につく前に先に登校していた塔次の席の正面に立ち塔次に詰め寄る。
「どうした土神、藪から棒に。そんなにめんたいこの港商品化の経緯が気になるのか?」
「何でこっちが聞きたいことを既に把握してんだよ!?」
「ふっ……そろそろその話を振ってくる頃合いだと思っていたからな」
「あぁそうかよ、だったら話は早い。何でアレが商品化してんだよ?」
不敵な表情を一切崩さない塔次に半眼で詰問する修也。
「最初に言ったではないか。きのこたけのこ論争の膠着状態を打破するために第三勢力を投入したいと」
「それが商品化に繋がるとか予想できるか! 俺はせいぜい文字通り論争に新たな話題を持ち込むくらいだと思ってたわ!」
「それでは何も面白くなかろう。一時的に話題にはなるかもしれんがすぐに消えてしまう」
「だからって実際に製菓会社に話を持ち込まんでも良いだろうに」
塔次の言わんとすることは分からなくもないが、そこで行動に出るのは違うだろうと修也はため息を吐く。
「しかしだな土神。いくら俺が案を持ち込もうと製菓会社が聞く耳を持たなければ商品化にまでは至らんぞ」
「う、いやまぁそうかもしれんが……」
塔次の言う通りアイデアを持ち込んでもそれが採用されるとは限らない。
それが採用されたということは、製菓会社もめんたいこの港のアイデアが良いと判断したということなのだろう。
「だからってあんな片手間で適当に思いついたものを……」
「世の中得てしてそういうものだぞ。真剣に悩んで何日もかけてひねり出したアイデアよりもふとしたきっかけで湧いて出たアイデアの方が有用だった例は少なくない」
「それは分からんでもないが……」
「別に良いではないか。土神には何の損にもならんのだぞ?」
「アレが陳列棚に並んでるのを見るたびに『やっちまった』感に苛まれるわ!!」
適当に考えた名前が全国レベルで晒されるとか公開処刑以外の何物でもない。
「落ち着け。名付け親が誰なのか世の中の大半は知らんのだ。堂々としておけばいい」
「簡単に言ってくれるな……」
「ああそう言えば製菓会社の広報担当が土神に連絡を取りたがっていたぞ」
低い声で呟く修也を無視して塔次は話を進める。
「広報担当の人が? 何で?」
「今回の新商品のアイデアを出してくれた礼ということで、売り上げの一部を土神の口座に振り込みたいらしい」
「……は?」
塔次の言葉に唖然とする修也。
「何、案ずることは無い。概算で1つ売れるごとに1円だ。大した額ではなかろう」
「いや……とは言っても……うーん…………」
次々と塔次からもたらされる新情報に段々頭がこんがらがってくる修也。
「まぁ全国規模で売り出す上に出足はそこそこ好調のようだから1つ1円とは言え馬鹿にはできんがな」
「マジかよオイ!?」
最早呆れてそんなおざなりなツッコミしか言えなくなってしまった修也であった。
守護異能力者の日常新生活記
~第4章 第9話~
「いやまさか、ここに来て第三勢力が現れるとは思いませんでしたわ」
「全くですぞ。自分としたことがチェックを怠るとは何たる不覚」
そこに白峰さんと黒沢さんがそろって登校してきた。
「チョコをイチゴチョコに変えたりいっそチョコを無くしたりしてきてはいましたが……」
「全くの新キャラを打ち出してくるとは侮れませんな」
内容から察するに話題は『めんたいこの港』のことだろう。
「では早速新キャラ、めんたいこさんのキャラメイクに移りますわよ!」
「合点承知!!」
「いっ……!」
『いきなり擬人化させるのかよ!!』というツッコミが喉元まで出かけたのをギリギリで抑える修也。
これは今まで以上に変に関わるとロクなことにならない予感がする。
「して、白峰殿はどのような方向性をお考えでありますか?」
「そうですわねぇ……私としてはつなぎと長靴が似合う、手ぬぐいをバンダナのように巻いている漁師が良いかと」
「ほほぅ! 中々渋い所を突きますな!」
「黒沢さんはどのようなキャラを想定しておりますの?」
「自分は幼い頃からの憧れである海兵になったばかりのまだあどけなさの残る少年が良いですぞ!」
「黒沢さんはやはり美少年の方向にベクトルが向いてますわね」
「そう言う白峰殿はイケオジ方向一直線ですな」
楽しそうに話題に花を咲かせる白峰さんと黒沢さん。
だがその花の色はかなり濁っているような気がする。
「では、既存のきのこ殿とたけのこ殿との絡みはいかがなさいますかな?」
「3人の爽やかな友情物語も描いてみたいですが、ドロドロとした愛憎漂う三角関係も捨てがたいですわね」
「自分は少年漫画のような展開も良いですし、NTR系にも挑戦してみたいですぞ!」
「流石黒沢さん! 新境地へ挑む飽くなき探求心が素晴らしいですわ!」
「白峰殿こそ基本に忠実なその姿勢にはいつも学ばせてもらっておりますぞ!」
「うふふ……うふふふふふふ……!」
「どぅふ……どぅふふふふふ……!」
またしても修也の理解の及ばない領域で盛り上がる2人。
「そうと決まれば早速原稿に取り掛かりますわよ黒沢さん!」
「テンション上がってまいりましたぞおおぉぉ!!」
「……あの2人は何しに学校に来てるんだ?」
「さてな。その答えを追求する気にはならん」
早速机を向かい合わせて原稿を描き始めた2人を呆れた目で見ながら呟く修也。
塔次は興味なさそうに吐き捨てる。
「それはさておき、土神の連絡先を教えても構わんか?」
「え? あぁさっきの広報担当の人の話か? 辞退したいんだけどなぁー……」
修也としてはあんな適当かつ投げやりな意見がまさか採用されて商品化にまでこぎつけられるとは考えもしなかった。
だからそんなことで謝礼を貰えると言われても正直申し訳ない気持ちでいっぱいだ。
それにこの町に引っ越してきてからというものの『お礼』と名の付くものをこれでもかというほど受け取っている。
それが華穂の家でのクレープパーティーの招待くらいなら良いのだが、他はどれもこれもウェイトが重すぎる。
そこから更に増えても扱いきれず途方に暮れることしかできない。
「まぁそう言うな。企業としてもアイデア料を払わないわけにはいかん。社会とはそういうものだ」
「うーん……」
「それに今更これくらい増えたところで微々たる差ではないか」
「明らかにこれだけ異質だよ!」
今までは曲がりなりにも人助けになっていたのでそのお礼ということで無理やり納得してきた。
しかし今回は明らかに人助けとは無縁だ。
予期せぬところから増えることが決まった謝礼に修也は割と本気で頭を抱えることになるのであった。
「ねぇねぇ土神くん」
昼休み、またいつもの面子で屋上で昼ごはんを食べた後、華穂がおもむろに話を切り出した。
「ん? 何だ華穂先輩」
「昨日ちょっとお買い物のついでにスーパーに寄ったんだけどさ、その時にこれを見つけたんだよ」
そう言って華穂が取り出したのは……めんたいこの港だった。
「ごふぅっ!!?」
「せ、先輩……!?」
急にむせ返った修也に詩歌が驚く。
「そんなリアクションをするってことは、やっぱりこれは土神くんがこの前話してたやつと関係があるんだね?」
「そ、そう言えば先輩には少し話してたっけな……」
修也は以前華穂に少しだけ話をしていたことを思い出す。
猪瀬に絡まれて鬱屈とした気分を吹き飛ばす話をしてほしいと言われた時にめんたいこの港について話した。
華穂はそれを覚えていたのだろう。
「何か俺の知らない所で商品化が決まってたらしいんだよ……」
「その話を聞いた時は私も驚きました……」
修也の言葉に苦笑しながら蒼芽が続く。
「俺、てっきり軽い冗談かささやかな話題の種くらいに思ってたんだけど、まさかのガチだったんだよなぁ」
「でも凄いじゃない! 実際に商品化されてるってことは、製菓会社の目に留まったってことだよ」
「それ同じこと言われたよ……でもあんな適当に言ったものが……」
「あ、あの……ところで……それ……美味しいんですか……?」
修也が項垂れている中、詩歌がそんなことを尋ねてくる。
「あ、うん。味は普通に美味しいよ。塩チョコだから何も知らずに食べるとちょっと驚くけど」
「あぁ、蒼芽ちゃんはもう食べたんだね。気になったから買って味を確かめてみようと思ってたんだけどおいしいなら問題ないね。皆で食べよっか」
そう言って華穂はパッケージを開けて1つ摘まんで口に入れる。
「あ、ホントに塩チョコだね。しかも中がビスケットだ」
「わ、私もひとつ……良いですか……?」
「うん、はいどうぞ詩歌ちゃん」
詩歌の言葉に華穂は頷いてパッケージを差し出す。
「………………」
めんたいこの港を口に入れ、味わう様に咀嚼する詩歌。
「……うん、チョコの風味が失われないかつしっかりと塩が効いているのが分かる絶妙な塩加減。それでいて中のビスケットの歯ごたえが良いアクセントになってる。チョコと塩とビスケットの風味と食感が良い感じに同調しているね」
真顔で一切どもらずつらつらと喋る詩歌。
「……流石詩歌。料理の事だと顔つきが違うね」
「……あっ! ご、ごめんなさい、私……」
蒼芽の呟きに我に返った詩歌が顔を赤くして謝る。
「別に謝ることじゃないよ。詩歌ちゃんがそれだけ褒めるってことはこれはやっぱり凄いお菓子だってことだよ」
「だから修也さんも気にしないでむしろ堂々と胸を張ってれば良いと思いますよ」
「いやそこは製菓会社の企業努力の賜物で俺関係無ぇよ」
蒼芽の微妙にズレた励ましに修也が突っ込んでいると……
「ん……? 電話か?」
修也のスマホが震えだした。
しかもメールなどの通知ではなく、通話の着信だ。
番号は見たことが無いものである。
「……誰だろう? 俺のスマホに電話かけてくるとかレア人物すぎるだろ」
「自分で言ってて悲しくならないですか修也さん」
「じゃあ私もレア人物だねっ! 土神くんに電話かけたことあるし」
修也の呟きに半眼で突っ込む蒼芽と何故か得意気な華穂。
「あ、あの……えっと……」
詩歌はどうしたら良いか分からずオロオロしている。
「とりあえず出てみるか……もしもし?」
修也は先程から震え続けているスマホに出る。
『もしもし、こちら土神様の携帯でよろしかったでしょうか?』
「はい、そうですけど……」
電話の相手は女性だった。
ただ、分かるのはそれだけだった。
聞き覚えの無い声に修也は首を傾げる。
『私、めんたいこの港販促プロジェクトの広報を担当しております永田と申します』
「っ!?」
しかし電話の相手が名乗ったことで修也は驚いて息をのんだ。
(ま、まさか本当に連絡が来るとは……!)
確かに塔次は広報担当の人が連絡を取りたいと言っていた。
こちらの心情はどうであれ無視するのは良くないと思ったので連絡先を教えることは了承したが、それでもこんなに早くコンタクトを取ってくるとは思わなかった。
『この度は弊社の新商品の為にアイデアを提供していただき、誠にありがとうございました』
「あ、いえ……そんな大したことはしてないんですが」
『いえいえ、我々には無い柔軟な発想で、目から鱗が落ちる思いでした』
「は、はぁ……」
流石に『それその場で適当に考えたやつです』とは言えず、曖昧に相槌を打つ修也。
『それでですね、代理人である氷室様より伺っているかもしれませんがアイデア料として売り上げの一部を土神様へお支払いさせていただくためにお電話をさせていただいたのです』
「あの、それなんですが……流石に何か申し訳ない気が……ただアイデアを出しただけなのに……」
『お気になさらないで結構です。そのアイデアを出すというのが一番難しいのです。何も無い所から形作る訳ですからね』
「そういうものですか……」
『という訳ですので、毎月末にその月の売り上げの1%を土神様指定の口座に振り込ませていただきたいのです』
「えっ!?」
永田さんの言葉に修也は驚きの声をあげる。
『1%しかお支払いできないのが申し訳ないのですが……』
「いやいやちょっと待ってください! 毎月末って言いましたよね!? 月ごとに振り込まれるってことですか?」
『それはもちろん、日を追うごとに売り上げは変わりますので』
「ええぇ……」
修也はてっきり1回限りだと考えていたのだが、永田さんの話だと継続的に売り上げの1%が振り込まれるらしい。
売上次第で変動するだろうが、少なくとも高校生の小遣いレベルの金額には収まらないだろう。
「いくらになるか知らないけど絶対持て余すって……辞退とかできませんか?」
『お気持ちは分かりますが、こちらも予算を組んでいる以上お渡ししないわけにはいかないのです。ご了承くださいませ』
「はぁ……分かりましたよ」
これは修也がごねてどうにかなるような物ではない。
そう思い修也は納得はできないものの了承することにした。
『それでは各種手続きがございますので直接お会いできればと思います。土神様のご予定に合わせますので、ご都合の良い日を教えていただけますか?』
「基本的に放課後の時間だったら大丈夫ですが……」
『それでは明日の午後4時にモール2階の喫茶店にお越しくださいませ』
「…………あぁ、あそこか」
修也は先日蒼芽にモールを案内してもらった時に一緒に行った喫茶店を思い出す。
『それでは、失礼します』
その言葉を最後に通話は切れた。
「…………俺、どうすれば良いと思う?」
「あ、あはは……」
スマホを持ったまま呆然としながら尋ねる修也に蒼芽は苦笑いしかできなかった。
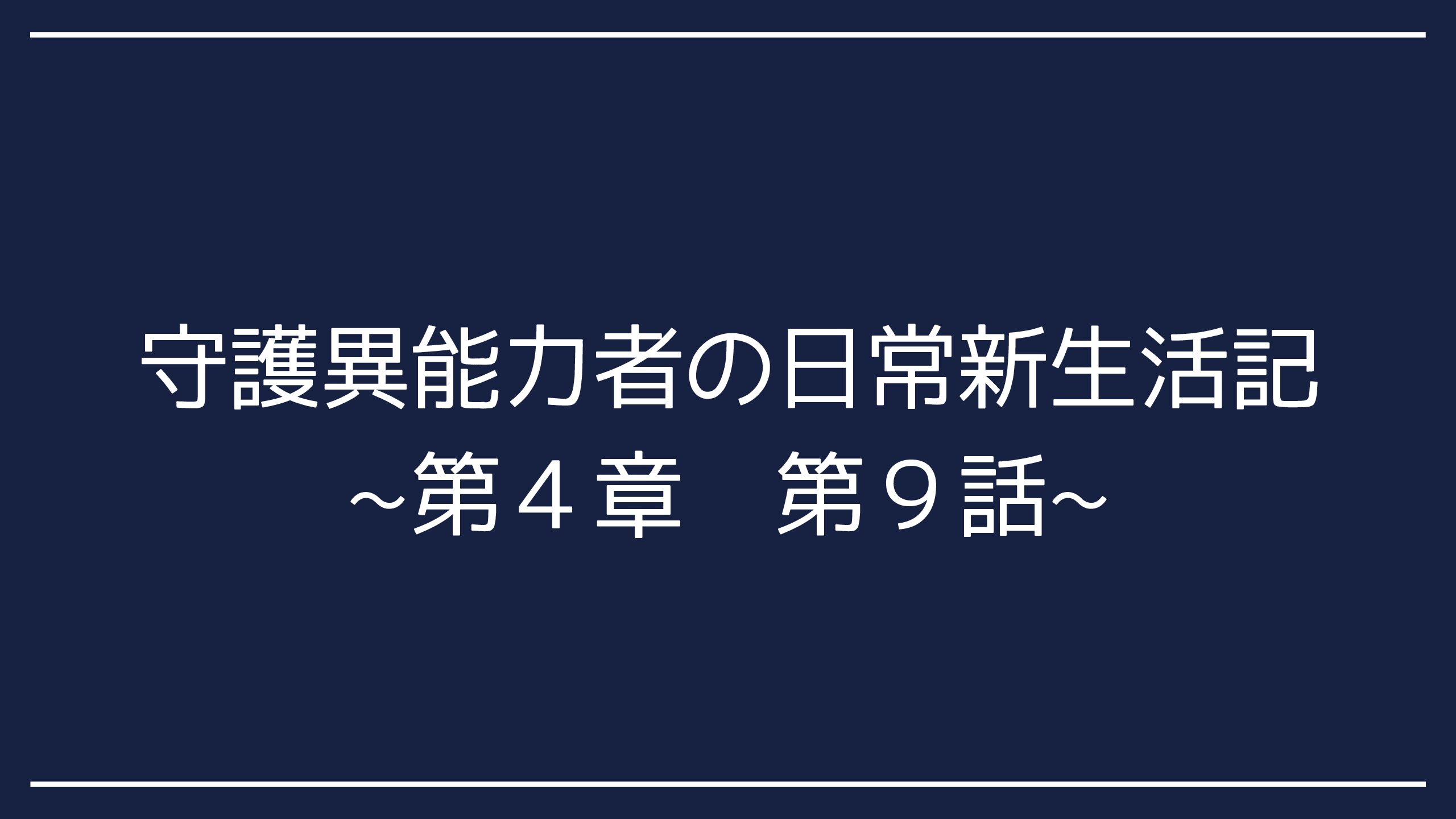

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]