(…………んー……もう朝か……)
めんたいこの港騒動のあった週の土曜日、修也はいつも通りの時間に目が覚めた。
とは言え、目が覚めたというだけでまだ起き上がる訳ではない。
時刻はまだ5時半。
今起きてリビングに行ったところで紅音は起きているが朝食の準備はまだできていないだろう。
それに加えて今日は授業も無い。
つまり急いで起きる理由が全く無いのである。
(……今週も色々あったなぁ……)
引っ越してきてからというものの充実はしているが色々と騒がしいことに巻き込まれている修也。
あまり自覚は無かったがちょっと疲れがたまってきてるのかもしれない。
しっかり寝たはずなのだが体がまだ少しだるい気がする。
今日くらいはちょっと寝過ごしてもバチは当たらないのではないだろうか。
まぁ元々修也は目が覚めるのは早いが起き上がるのは普通の時間という生活スタイルだ。
何だかんだ言っても結局はいつも通りの生活リズムになるのだろう。
(それに目は覚めてるけどこうやってベッドでうだうだしてる時間もそれはそれで……)
休日の早朝というたっぷりと自由な時間が取れる事実が修也に心の余裕を持たせる。
せっかくなら普段はやらない二度寝までやってしまおうかと修也が考え出したその時。
「おにーさんおっはよー!!」
「ぶほぉっ!!?」
突然修也の腹部に上から衝撃と重みが加わった。
予期せぬ衝撃に修也は肺の空気を強制的に押し出され、軽い呼吸困難に陥る。
「な、何だ何だ……!?」
「おにーさん朝だよー! 起きて起きてー!!」
「ゆ……由衣ちゃん?」
「うんっ! おにーさんおはよー!」
「お、おはよう……」
朝から修也を呼吸困難というプチ修羅場に誘い込んだのは由衣だった。
由衣は修也のベッドに飛び込んで、そのまま修也に跨ってきたのだ。
いくら由衣が軽いとはいえ、完全に不意打ちの形で飛び乗られたら修也だって驚く。
「朝から元気だなぁ、由衣ちゃんは……」
朝は中々調子の上がらない修也としては、こんな時間でも元気いっぱいの由衣が少し羨ましい。
「うんっ! 私はいつでも元気だよー!」
修也の呟きに笑顔全開で答える由衣。
「だって今日は土曜日で学校はお休みなんだよー? だから1日ずっと遊べるんだよー!」
「あー、その気持ちは分かる。休みの日って何かウキウキするよな」
「だよねー! 平日は学校の友達と遊べて楽しいけど、土日はまた違った楽しみがあるんだよー!」
そう言う由衣は本当に楽しそうである。
「由衣ちゃんは何に対しても楽しそうだなぁ」
「うんっ! 同じ1日を過ごすなら楽しい方が絶対に良いもん! それにねー……」
そこで一旦言葉を区切り、由衣は修也のベッドから飛び降りる。
「今日はおにーさんとおねーさんと一緒にプールに遊びに行くんだもん! 楽しくないわけが無いよー!」
そして喜びを表現しているのか両手両足を大きく広げながら由衣はそう言葉を繋げた。
守護異能力者の日常新生活記
~第4章 第12話~
「あぁ、そういやそんな話してたっけな」
修也は昨日の夜の事を思い出す。
夕飯を食べ終えて自分の部屋に戻ったら、由衣がまた遊びにやってきていた。
蒼芽も加えた3人で遊んでいたのだが、その時の話の流れでプールに行こうということになったのだった。
「しかしまぁ急な話なことで……」
「でもせっかく水着買ったんだもん。使わなきゃもったいないよー」
「まぁそれは分からんでもないが……季節的にちょっと早くないか?」
確かにもうすぐ夏がやってくる季節ではあるが、あくまでも『もうすぐやってくる』だけであってまだ夏ではない。
最近暑くなってきたとは思うが、だからと言ってプールで遊ぶにはまだ少し肌寒い気もする。
「プール開きしてるのかちゃんと調べないと……」
「ほえー? おにーさん、あのアミューズメントパークのプールは1年中やってるよー?」
「……え?」
プールに行こうという話だけが先行していてそもそも営業しているのかを修也は確認していなかった。
なのでスマホを開いて調べようとしたが、由衣の言葉にその手が止まる。
「え……1年中って、真冬でもやってんの?」
「うんっ! やってるよー」
「俺ここの冬がどんなのか知らないけど、冬でもプールに入れるほど暖かいとか?」
「違うよー。屋内プールだからだよー」
「あぁ、そういう……」
屋内プールということは空調も完備されているのだろう。
確かにそれなら冬でもプールで遊ぶことができる。
「……でもあえて冬にプールへ行く意味あるか?」
「んー……よく分かんないねー」
修也の疑問に思案顔で首を傾げる由衣。
修也もよく分からないが、需要があるから年中営業しているのだろう。
「ところで由衣ちゃんはそのアミューズメントパークのプールに行ったことあるのか?」
これ以上深く詮索しても仕方がないと修也は思い、話題を変える。
「うぅん、無いよー。だからどんなところなのか楽しみなんだよー」
修也の問いかけに首を横に振る由衣。
「俺もこういう類の場所には行ったことが無いからちょっと楽しみだな」
「へぇー、おにーさんもなんだねー」
「まぁな」
一緒に行くような友達がいなかったというのも間違いではないが、そもそもそういう施設が引っ越し前の町には無かった。
なので人間関係の事情は関係なしに夏にプールへ遊びに行くという経験は修也には無い。
(そう……関係ない……よな? 実は俺の知らない所でそういうイベントがありました、とかは流石に無い……よな?)
考えているうちに段々修也は自信が無くなっていく。
もしかしたらもしかするかも……? という考えが頭の中で膨れ上がっていく。
「おにーさん、今日は一日いーっぱい遊ぼーねー!」
そんな修也の心境など露知らず由衣はプールへ遊びに行くのを本当に楽しみにしているようだ。
(……まぁ良いか。昔がどうだったかなんてもうどうでも良いや)
今はこうやって一緒に遊びに行く相手がいる。
昔がどうだったかなんて関係無い。
修也は暗い考えを振り払い、気を持ち直す。
「……そうだな。今日は目一杯遊ぼう」
「うんっ!」
修也の言葉に由衣は笑顔で頷くのであった。
「……相変わらず混雑具合がヒデェ……」
アミューズメントパークに行くために電車に乗った修也たちだが、相変わらずの電車の混みように修也はげんなりしていた。
何とか目的の駅に着いたものの、今は駅のホームで小休止している。
「確かに3駅だけとはいえ凄い混みようでしたね」
「それだけこのアミューズメントパークが人気ってことなんだろうけどさ」
「でもこーゆーのも楽しいよー!」
蒼芽も修也と同じく来ただけで少し疲れた様子を見せているが、由衣にはそう言った雰囲気は全く感じられない。
「由衣ちゃんは前向きだなぁ」
「だってねー、電車の中は人でいっぱいだったけどそのおかげでずーっとおにーさんとぎゅーってできたんだもん!」
「え、そういう理由?」
確かに由衣は電車に乗っている間ずっと修也にしがみつきっぱなしだった。
「なるほど……それは確かに」
「え、納得できちゃうの?」
ついでに蒼芽も空きスペースを確保して修也にしがみついていた。
満員電車だったので傍から見て不自然さは無かった。
妙に服を引っ張られる感覚があるとは思っていたが、それは2人が修也にしがみついていたからのようだ。
「前に言ったじゃないですか。修也さんに抱きしめられると凄く落ち着くって」
「あぁ、そう言えば……」
修也は先日蒼芽に言われたことを思い出す。
あの日の夕飯後約束通り蒼芽を抱きしめることになった修也だが蒼芽が全く離れてくれなくなり、紅音が風呂が沸いたと階下から呼ぶまでずっとその体勢のままだったのだ。
「おにーさんはきっと癒し系なんだよー」
「いやそれは無い……っていうか多分言葉の使い方が違う」
「じゃあ修也さんは癒し系にどんなイメージを持ってますか?」
「え? そうだなぁ……」
蒼芽に問われて修也は少し考える。
「側にいるだけで安心できるような……落ち着くというか……こう、心が癒される感じ?」
非常に曖昧ではあるが修也は癒し系に対する自分のイメージを述べる。
「じゃあやっぱりおにーさんは癒し系だよー!」
「だね」
「え、いや何で?」
確信を得たと言わんばかりに断言する由衣。
何故か蒼芽まで同調しだしたことに修也の頭の中は疑問でいっぱいだ。
「だってー、おにーさんと一緒にいると何だか安心するしー」
「落ち着きもしますしね。修也さんの側なら安全だって」
「これって心が癒されてるってことだよねー?」
「えぇー……」
2人の言い分に言葉が詰まる修也。
「でもそれって蒼芽ちゃんと由衣ちゃんがそう思ってるだけって可能性も……」
「だったら詩歌や姫本先輩にも聞いてみますか?」
「やめて! 話を無駄に広げないで!!」
「じゃあおにーさんは癒し系ってことで決定だねー!」
「いやいやいやいや……」
修也自身は自分を癒し系だなどと思ったことは一度も無い。
なので由衣の言葉にただただ戸惑うばかりだ。
「良いじゃないですか修也さん。私は素敵だと思いますよ? 癒し系の修也さん」
「う、うーん……俺自身としては癒し系とは対極の位置にいると思うんだが……」
これなら陽菜に言われた『生粋のツッコミスト』の方がまだしっくりくる。
「少なくとも私と由衣ちゃんは修也さんのことを癒し系だと思ってます」
「うんっ!」
「そんな評価下されたの生まれて初めてだよ……ま、それは置いといてそろそろ行こうか。蒼芽ちゃんも大丈夫か?」
軽く雑談したことで気分が戻った修也は立ち上がり蒼芽に尋ねる。
「はい。私は大丈夫です」
「じゃあしゅっぱーつ!!」
由衣の号令を合図に、修也たちはアミューズメントパークの入り口に向けて歩きだした。
「……あっ! 入り口が見えてきたよおにーさん!」
駅を出てすぐ見えてきた入り口を指さして由衣が声をあげる。
「見えてきたっつーか……駅を出たらあるっつーか……」
「あ、あはは……」
「前来た時も思ったけど、駅を出てすぐ入り口があるのってどうなんだろうな……?」
「私は楽で良いと思いますよ?」
「まぁそれは否定しない。それじゃあさっさと受付済ませてしまおうか」
そう言って修也は入場口に向かう。
「あれー? おにーさん、まずはチケットを買わないといけないんじゃないのー?」
チケット売り場に行かず入場口に直行した修也を不思議に思った由衣が尋ねてくる。
「あぁ、多分大丈夫。本当にこれが使えるのか分からないけど……」
そう言って修也は自分の財布から1枚のカードを取り出した。
「ようこそいらっしゃいませ。入場券かフリーパスのご提示をお願いします」
入場口に控えていたスタッフが修也に近づき話しかけてくる。
「えーっと、これ使えますかね?」
そう言って修也は持っていたカードをスタッフに見せる。
「こ……これは……!!」
そのカードを見たスタッフの表情が驚きに染まる。
「も、申し訳ありません。少々お時間を頂いてもよろしいですか?」
「え?」
何やら慌てだしたスタッフに修也は首を傾げる。
「……もしかして偽造とかその辺を疑われてる? そりゃ有効期限が『9999/12/31』ってなってたら怪しさ大爆発だけど」
修也がスタッフに見せたカードは以前ここのオーナーから貰った永年フリーパスだ。
世に2つと無いこんな物を見せられたらそんな対応になっても不思議ではない。
修也はそう思ったのだが……
「いえ、そうではありません。とにかくこちらへどうぞ。お連れ様もご一緒に……」
そう言って修也たちを従業員専用の部屋へ案内するスタッフ。
よく分からないが悪いことではなさそうなので修也たちは首を傾げながらも案内されるままに部屋に入っていった。
「……で、何かと思えば……」
今修也たちはスタッフ専用の部屋で並んでソファーに座っている。
「はっはっは、また会えて嬉しいよ土神君!」
そしてその修也たちに向かい合う様に座っているのは、修也に永年フリーパスを渡した張本人であるオーナーだ。
「僕がスタッフに頼んでいたんだよね。そのカードを見せてきたお客さんが来たら僕を呼んでくれって」
「いやそんな大げさな……」
ただの一利用客の為にオーナーが出張るとか話が大仰すぎると修也は思うのだが……
「何を言うか! 君のおかげであの事件は被害者ゼロで翌日から通常営業に戻れたんだ。いわば君はここの恩人なんだよ! だからこのもてなしも妥当なものさ」
それを真っ向から否定するオーナー。
「こうしてオーナーが言っていると本当なんだなって改めて実感しますね」
「やっぱりおにーさんは凄いよー!」
修也の両隣に座っていた蒼芽と由衣がそんな感想を述べる。
「そうだよお嬢さんたち。彼はそれだけのことをしたんだよ」
「でもそのお礼はこの永年フリーパスでしてもらってそれで終わりなのでは……?」
修也としてはそれでも過剰なお礼だと思ってるのだが、無理やりそういうものだと自分を納得させていた。
だからこれ以上のことは無いと思っていたのだが……
「だってさぁ土神君、理事長の孫娘を助けたお礼で学費完全免除になったでしょ? だから僕も負けてられないんだよ!」
「だから何で変な所で対抗意識燃やすんですか!」
無駄に張り切って目を輝かせているオーナーに突っ込む修也。
「まぁまぁ落ち着いて。今回はこれを渡したいだけだから」
そう言ってオーナーは紙切れを修也に差し出す。
「これはパーク内の飲食施設で使えるチケットだよ。それを見せれば1回分の会計が無料になる」
「……つまり今日の昼食代をオーナーが持ってくれるということですか」
「まぁそう取ってもらえればいいよ。どうだいこれくらいなら気兼ねしなくていいだろう?」
「……まぁ、そうですね……」
学費完全免除や永年フリーパスに比べれば今回は随分と規模が小さい。
今までのお礼の規模が大きすぎて感覚が麻痺している感じが否めないが、修也は無理やり自分を納得させることにした。
「じゃあ今日は目一杯楽しんでいってくれ! それじゃあね」
そう言ってオーナーは立ち上がり部屋から出ていった。
「……まさかあの人、これだけの為にここまで来たのか?」
「さ、さぁ……どうなんでしょう……?」
金持ちの考えることはよく分からない。
修也と蒼芽はオーナーが去っていった扉をそんな思いを抱きながらしばらくの間呆然と見つめていた。
ちなみに由衣は修也が受け取ったチケットを物珍しそうな目で観察していた。
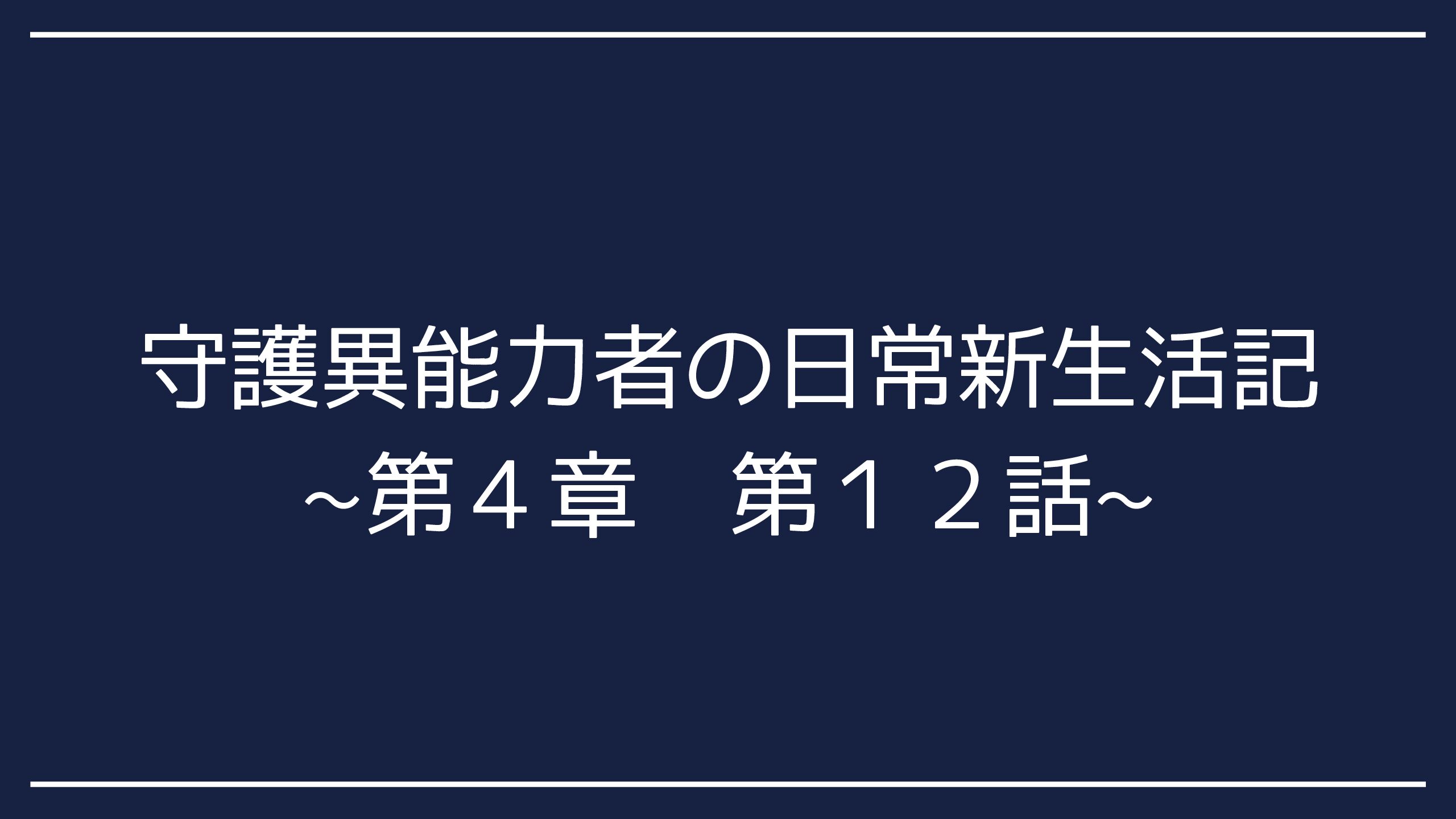

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]