「おいしいねー、おにーさん」
「そうだなぁ、屋台で作られてるものって何か不思議な魅力がある」
焼きそばとたこ焼きを2皿ずつ買ってテーブルに並べた修也たちはそれぞれ自分の分を食べる。
「確かに美味しいですけど……修也さんはそれで足りますか?」
たこ焼きを1つ口に入れながら蒼芽が尋ねてくる。
普段の修也の食事量を知っている故の疑問なのだろう。
「まぁ足りなきゃ追加で何か頼むよ。どれだけ頼んでも金かからないっぽいし」
「え? そうなんですか?」
修也の言葉に意外そうに首を傾げる蒼芽。
「オーナーは1回の会計が無料になるチケットをくれた。そしてここのシステムは最後に纏めて会計するものだ」
「あ……つまり途中経過はどうであれ会計は1回だけ。そしてその1回が無料になるから……」
「そういうこと」
「あっ! じゃあ私後でかき氷食べたーい!」
修也と蒼芽の話を横で聞いていた由衣が手を挙げてそういう。
「さっきも食べたいって言ってたもんね由衣ちゃん」
「うんっ!」
「あ、そういやかき氷で思い出したんだが以前蒼芽ちゃんがかき氷ってどれも味が同じって言ってたよな?」
引っ越して間もない頃そんな話が出てきたのを思い出した修也が蒼芽に尋ねる。
「あ、はい。ちゃんとしたところは知りませんけど、こういう屋台で作られているものは色と香りを変えているだけで味は同じなんですよね」
「えー、そーなのー? イチゴ味はイチゴの味がするよー?」
「うん、だからそれはイチゴの香りがするシロップをかけてるからなんだよ」
疑問顔の由衣に蒼芽が説明する。
「……だったら確かめてみようか」
「え?」
「ほえ?」
修也の提案に蒼芽と由衣はきょとんとした顔で修也を見つめる。
「これ食べ終わった後、それぞれが違う味のかき氷を頼む。そして目を閉じ鼻をつまんで食べてみるんだ」
「あ、なるほど。視覚と嗅覚を封じて味覚だけで食べ比べるんですね?」
「あっ! それ面白そー!!」
修也の説明と蒼芽の補足を聞いた由衣が楽しそうに目を輝かせる。
「それじゃあまずはこの焼きそばとたこ焼きを食べちゃおうか」
「そうですね」
「うんっ!」
修也の言葉に2人は頷いて食べるのを再開する。
「で、話は戻りますが……修也さん、それで足りますか?」
「……多分足りないな」
1皿に盛られている焼きそばの量はそこまで多くない。
たこ焼きも1舟6個と少々物足りなさを覚えるレベルだ。
蒼芽や由衣ならそれでも十分かもしれないが、修也としてはもう少し欲しい。
「あっ! だったら私の少し分けてあげるよー!」
そう言って由衣は自分の焼きそばを割りばしですくい上げて修也の分の皿に入れようとする。
「だったら私のも分けてあげますよ」
由衣に倣って蒼芽も自分のたこ焼きを爪楊枝で刺して修也の口元に運ぼうとする。
「いやいや足りなきゃ追加で頼むから良いって。気遣いはありがたいけど」
そんな2人の申し出をやんわりと断る修也。
(やっぱ2人だと食べ物のシェアとかもよくやってたんだろうなぁ……蒼芽ちゃんも由衣ちゃんもコミュ力抜群だしそれが普通なんだろうな)
そんなことをぼんやりと考える修也に対し……
(…………はっ!? よく考えたらこの爪楊枝私が口付けてる! しかも修也さんに直接食べさせようとしてた!! 私ったらなんてことを……)
内心真っ赤になって悶える蒼芽。
(……やっぱりおにーさんは凄いなー。私とおねーさんが分けた分を食べてもまだお腹いっぱいにならないんだー)
一方で由衣はのほほんとそんなことを考えながら修也を尊敬の眼差しで見つめていた。
守護異能力者の日常新生活記
~第4章 第15話~
「……さて、そういう訳で今俺たちの目の前には3つのかき氷がある訳だが」
結局追加でフランクフルトを食べた後、修也たちはかき氷を3つ頼んだ。
味はイチゴ・レモン・メロンの3つだ。
色も分かりやすく赤・黄色・緑と分かれている。
「……とっても単純な問題なんだが、目を閉じたらどこにあるか分からなくなっちゃうんじゃね?」
「えぇ……今更ですか? 修也さんならかき氷の気配とか分かるかと思ってたんですけど」
「いや流石に無理。そもそもかき氷の気配って何」
「あっ! だったら私が食べさせてあげるよー!」
根本的な問題で立ち止まった修也と蒼芽を見て由衣が手を挙げてそう言う。
「え?」
「目を閉じて鼻をふさいでも耳は聞こえるでしょー? それなら食べさせるのは簡単だよー」
「あぁーなるほど。確かにそれならいけそうだ」
「じゃあおにーさん、目を閉じて鼻をふさいでー」
由衣に促されるままに修也は目を閉じて鼻をふさぐ。
「じゃあ行くよーおにーさん。あーんしてー」
「あー……」
そう言って修也が口を開けると同時に舌の上に冷たい塊が乗せられた。
由衣がどれかのかき氷を口に入れたのだろう。
しかし『甘い』と『冷たい』しか感じ取れず、何の味かまでは分からなかった。
「え……何味だコレ? 全然分からんぞ?」
「じゃあ次はこっちです修也さん。口開けてください」
「あ、あぁ……」
蒼芽に促され再び口を開ける修也。
また冷たい塊が口の中に入るが、結果はさっきと同じだ。
「……うん、やっぱり冷たいのと甘いのしか分からん」
「じゃあ次は私がやってみたーい!」
今度は由衣が味見する役をやりたいらしいので交代する。
「それじゃこれ行ってみるか……ほれ由衣ちゃん、口開けて」
「あーん……」
目を閉じて鼻をふさいだ由衣が大きく口を開けたので、修也はイチゴ味のかき氷をすくって口に入れる。
「わっ! 冷たーい!! ……でも何味なのかは分かんないねー」
由衣も修也と同じ感想を持ったようだ。
「じゃあ由衣ちゃん、これは?」
そう言って蒼芽はメロン味のかき氷を由衣の口に入れる。
「んー……甘いのと冷たいのは分かるんだけどー……」
「よし、蒼芽ちゃんもやってみよう」
「あ、はい。やってみます」
そう言って蒼芽が目を閉じて鼻をふさいだのを確認してから修也はレモン味のかき氷を蒼芽の口に入れた。
「……? 冷たくて甘いですけど……これ何味ですか?」
「やっぱ分からんもんなんだなぁ」
「不思議だねー」
結局誰も味の区別をつけることができず、残りのかき氷は普通に食べることにした修也たち。
「先日白峰さんと黒沢さんが言ってた、五感を使って食を楽しむってのに通づるものがありそうだなぁ」
「ご飯って味だけじゃなくて見た目とか匂いも大事なんだねー」
「そう言えばブルーハワイ味ってありますけどあれは何の香料なんでしょうか?」
そんな取り留めも無い話をしながら修也はレモン味、蒼芽はメロン味、由衣はイチゴ味のかき氷を食べていく。
「あ、ゴメン蒼芽ちゃん。ブルーハワイ味もあったのにすっかり失念してた」
「いえ、別に何が何でも青が良いという訳では……」
「でもおねーさん青好きだよねー。さっき着替える時に見えたけど青いネックレス着けてたしー」
「あれは青いからというより修也さんに買ってもらったから気に入ってるんだよ」
「へぇー、そーなんだー」
「でも今は着けてないんだな」
修也の指摘する通り今蒼芽の首周りには何も着けられていない。
「こういう所では装飾品は着用禁止ですからね。そうでなくても何かの拍子に落としたりしたら大変ですから」
「言われてみれば確かにそうか」
修也自身は気にすることが全く無かったので失念していたが、確かにこういう所では装飾品は外すように注意書きが各所に貼られている。
それにやたらとスリルを求めるアクティビティがあるこのプールだと落としてしまうリスクも多分にある。
「いーなー、私もそーゆーおしゃれしてみたいなー」
「じゃあ今度一緒にモールへ見に行こっか。これもモールの雑貨屋さんで買ってもらったし」
「うんっ!」
蒼芽の提案に笑顔で頷く由衣。
「それはそれとしてそろそろ昼も終わりにするか」
かき氷の器が3つとも空になったのを見て1つに纏める修也。
「あ、そうですね」
「うんっ! お昼からも遊ぶよー!」
それを見て蒼芽と由衣も席を立つ。
纏めたかき氷の器をゴミ箱に捨て、修也たちは再びプールへと向かって歩いていった。
「そうそう、こういうの。俺が想像してた流れるプールってのはこういう奴だよ」
修也はゴムボートのヘリにつかまりながらゆっくりとした水の流れに身を任せていた。
やたらとスリルのあるアクティビティばかりが目についていたが、こういうジャンルの物もきちんと用意されていたらしい。
「ゆっくり流れていくのも楽しーねー、おねーさん」
「そうだね。私はこれくらい落ち着いてる方が楽しめるかな」
ゴムボートの上では蒼芽と由衣が楽しそうにはしゃいでいる。
「由衣ちゃん、てっきり昼前のようなスリルある方が好きだと思ってたけど、こういうのも好きなんだな」
「うんっ! 私は楽しい物なら何でも好きだよー!」
「うん、そうやって何にでも前向きに楽しめるってのは良いことだと思うぞ」
「えへへー、おにーさんが褒めてくれたよおねーさん!」
「良かったね由衣ちゃん」
「うんっ!」
修也はただ何となく思ったことを口にしただけなのだが、それでも由衣はにこにことご機嫌だ。
そんな由衣を見ていると修也も何だか嬉しくなってくる。
「あー……平和だ。すっげぇ平和。こっちに引っ越してきて初めてこんなまったりした時間を過ごしてる気がする」
「あ、あはは……」
修也の心の底からの呟きに蒼芽は苦笑する。
修也が引っ越してきてからというものの、変な事件が立て続けに起きてきた。
幸いなことに被害はほぼゼロで片付いてはいるが、落ち着いた平和な生活とは遠くかけ離れてしまっている。
だが今日は本当に何事もなく普通の学生らしい生活を満喫できている。
蒼芽がナンパに遭ってしまったが、今までの事と比較したら些細な出来事だ。
これもある意味普通の生活のイベントの一環とも取れる。
何も考えずゆっくりできる時間の大切さを修也はしっかりと実感していた。
「おねーさん、おにーさんどーしちゃったのー?」
「えっと……今日ここに遊びに来れて良かったねって話をしてたんだよ」
由衣の質問に蒼芽は当たり障りのない言い方で答える。
確かにわざわざ今まで起きた事件の数々を説明する必要も無いだろう。
それに遊びに来れて良かったというのも間違いではない。
「さて、これ1周したらそろそろ帰ろうか」
「えー、もっと遊びたーい」
修也の言葉に由衣は不服そうに頬を膨らませる。
「あまり遅くなると家の人も心配するからな。フリーパスはあるんだしまた来れば良いさ」
「そうだね。その時は由衣ちゃんも新しい水着を着れば良いんじゃない?」
「え? おにーさんおねーさん、また一緒に遊びに行っても良いのー?」
「あぁ、もちろんだ」
「うん、また来ようね」
「やったー! ……あ、でもー、おにーさんとおねーさんのデートの邪魔にならないー?」
修也と蒼芽の言葉に両手を挙げて喜ぶ由衣だが、すぐに心配そうな表情になる。
「まぁそれはそれで別枠をとれば……」
「えっ? 良いんですか!?」
何の気は無しに呟いた修也の言葉にかぶせ気味で問い返す蒼芽。
「え?」
「由衣ちゃんを入れて3人で遊ぶのとはまた別で私とデートしてくれるんですか!?」
「あ、あぁ……蒼芽ちゃんさえ良ければな」
「修也さんからのお誘いを断るわけないじゃないですか!」
そう言う蒼芽の目は建前や社交辞令の意思など微塵も感じられない。
本気で修也とのデートが楽しみだと告げている。
過去に似たようなやり取りをしたこともあるので蒼芽がそういうことをお世辞で言う子ではないと修也も分かってはいるのだが、やはりこうやって喜んでくれるのは嬉しいものだ。
「良いなーおねーさん。ねーねーおにーさん、私ともデートしてー」
「え? 由衣ちゃんも?」
修也と蒼芽に割り込むように由衣がそう言いだした。
「うんっ! 私もおにーさんと夜景の見えるレストランでワインで乾杯したーい!」
「はい? 何だそりゃ?」
突如意味の分からないことを言い出した由衣に首を傾げる修也。
「この前デートってどんなことするのかなーって調べたらそーゆーことするって漫画に描いてんだよー」
「どんな漫画だそれ……」
「由衣ちゃん、私たちは未成年だからワインは無理だよ」
「あ、そっかー」
「いや蒼芽ちゃんも止めるのそこだけ?」
「あはは……夜景の見えるレストランは私も良いなって思っちゃいましたから……」
修也の突っ込みに照れ笑いで返す蒼芽。
「はぁ……でも流石に夜景の見えるレストランは無理。せいぜいファミレスがいいとこだ」
「それでも良いよー! おにーさんとデートできるなら何だって楽しいと思うしー」
「そうですよ。『何を』よりも『誰と』の方が大事です」
修也の妥協案に嫌な顔を微塵も見せず笑顔で頷く2人。
そんな話をしているうちに流れるプールを1周してスタート地点に戻ってきた。
「よし、それじゃあ着替えて帰ろうか」
「はい」
「うんっ!」
修也の言葉に蒼芽と由衣が頷き、ゴムボートを近くにいたスタッフに返却した後、着替える為に更衣室へと引き上げた。
「……本当に良いんですか?」
「はい。オーナーからお話は伺っております。お代は結構です」
一足先に着替え終わった修也はフロントで清算を行っていたのだが、チケットを提示したら本当に0円になった。
本当に良いのか確認したのだが、問題無いと太鼓判を押されてしまった。
「うーん……何か悪い気が」
「おにーさんお待たせー!!」
「がっふぅっ!!?」
ここまで良くしてもらって逆に何だか悪い気がしてきた修也に真横から衝撃が襲い掛かる。
言わずもがな、由衣が飛びついてきたのだ。
「お待たせしました修也さん」
「あぁいや、大して待ってないから大丈夫」
「おにーさん難しい顔してたけどどーしたのー?」
「あー、ホントに会計が無料になっちゃったから驚いてただけ」
「確かにあれだけ食べて遊んで0円は何だか悪い気もしますね……」
「だろ?」
そんなことを話しながらプール施設を後にする修也たち。
(…………ん?)
その時修也は何か視線を感じたような気がして振り返る。
しかし辺りは他の利用者やスタッフでごった返しているだけだ。
これだけいれば修也たちに意図せず視線を向ける人が何人かいたっておかしくない。
「? どうしたんですか修也さん?」
修也の様子が気になった蒼芽が尋ねてくる。
「……いや、何でもない。帰ろ帰ろ」
感じた気がする視線を自分の気にしすぎだと結論付け、修也は違和感を振り払うのであった。
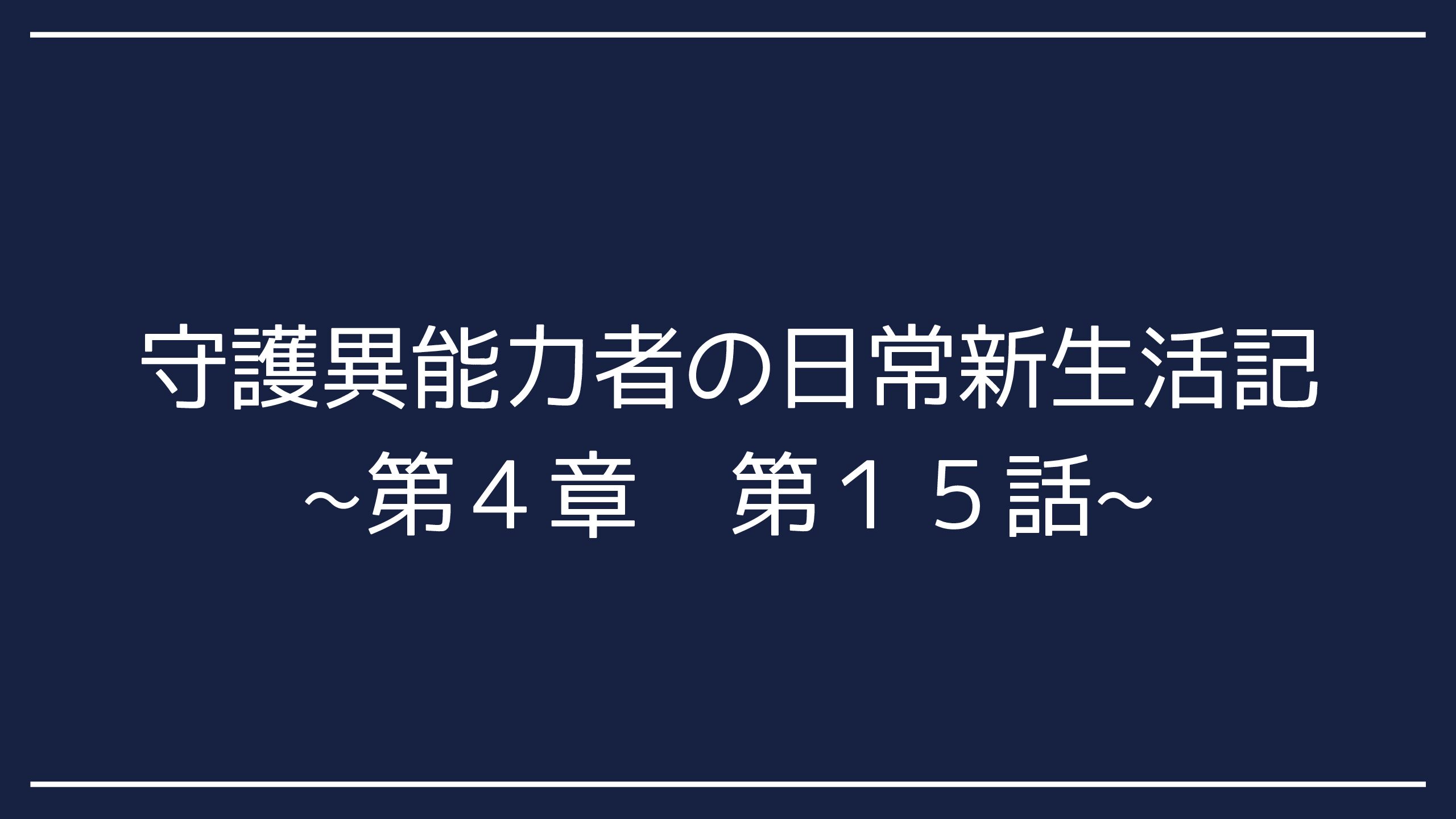

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]