その後まだ来ていなかった面子も続々と集合場所へとやってきた。
詩歌と爽香と彰彦は15分前に揃ってやってきて、塔次が10分前に現れて5分前に最後の亜理紗が到着した。
「あー、やっと来たー! もー、遅いよありちゃーん」
「えっ? もう全員揃ってるの? あれ、私時間間違えた? ちゃんと約束の5分前に来たと思ってたんだけど」
「いや大丈夫、間違えちゃいないぞ。他の面子が早すぎただけだ。俺も含めて」
他の全員が既に揃っているのを見て焦る亜理紗を修也はフォローする。
「えっと……参考までに聞きたいんですけど、皆さん何分前に来られたんですか?」
「俺は10分前だ。待ち合わせなら5~10分前に集合していれば特に問題は無かろう」
「私たちは15分前よ。何かあっても大丈夫なように大体これくらいに到着できるようにしてるわ」
「ふむふむ、なるほど……」
塔次と爽香の言葉に頷く亜理紗。
「俺たちは30分くらい前だな。なんやかんやでそんな時間になった」
「物凄く端折りましたね……蒼芽先輩もいたのにどうしてそんなことになったんですか?」
「あはは……まぁ色々あってね……」
亜理紗の問いに蒼芽は言葉を濁す。
「私もおにーさんたちと一緒に来たんだよー」
「あたしも同じくらいの時間だったなー! 適当に家出たらそんな時間になった!」
「いや由衣は土神先輩たちに合わせたとかで分かるから良いけど千沙は時計くらい見なさいよ。遅刻したらどうする気よ?」
「大丈夫大丈夫! 今まで遅刻したことなんか無いぜ?」
「あぁ、マジで千沙は遅刻したこと無いぞ。約束の時間の30分以内には必ずやってくる」
自慢気に言う千沙に瑞音が補足する。
「で、私も大体土神たちと同じくらいだ。私はいつもそれくらいの時間に来るようにしている。早すぎて困ることなんてあまり無いからな」
「私と美穂ちゃんは45分前くらいだったかな。皆で遊びに行くのが楽しみでついつい」
「普段は土神さんや瑞音さんと同じくらいなのですが、姉さんが急かすもので……」
あっけらかんと言う華穂に対して困ったような顔をして呟く美穂。
「俺は1時間前には来てたな。待ってる間はこれでトレーニングしてた!」
そう言って戒は手に持っていたものを見せてくる。
「ん? 何だコレ」
「これはハンドグリップだな。握力を鍛える為に使われるトレーニング器具だ」
彰彦の疑問に対し塔次が答える。
「まぁ、流石は戒さんです。少しの待ち時間も無駄にせず鍛錬に励んでおられるのですね」
「いえいえ、俺が好きでやってるだけなので……」
心底感心したような表情で賞賛の言葉を述べる美穂に照れ笑いする戒。
「まぁトレーニングは霧生君らしいから良いとして、そんなに早く来なくても」
「爽香、察しろ」
あまりにも早く集合場所にやってきたことに疑問を呈しようとした爽香を修也が諫める。
「あぁ……」
「やっぱりそういう……」
「まぁ霧生らしいではないか」
修也の言葉で大体の事情を把握したクラスメイトの3人は生暖かい視線を戒に送るのであった。
守護異能力者の日常新生活記
~第5章 第27話~
「……で、ボウリング場って何処なんだ? 俺知らないんだけど」
全員集まったので移動しようということになったのだが、修也はボウリング場がある場所を知らない。
「私も知らなーい。行ったこと無いもん」
「す、すみません……私も、知りません……」
それに対し由衣と詩歌も首を横に振る。
(まぁ……詩歌には縁の無さそうな場所だもんなぁ……)
修也にはボウリングとはリア充たちの遊びの内の1つというイメージがある。
そしてそのリア充の一般的なイメージには詩歌はどうしても結びつかない。
(…………それは俺も同じか)
修也自身引っ越し前も含めて一般的なリア充とは程遠い生活を送ってきている。
今でこそ大分改善されているものの、やはり修也が考えるようなリア充の生活ではない。
ただあくまでも『一般的な』というだけであって、そこからいくらかけ離れようとも修也は今の生活に不満は無い。
というか蒼芽みたいな可愛い女の子と一緒に暮らして身の回りの世話もしてもらっている生活に不満があるなんて言ったらバチが当たりそうだ。
「土神、あのチケット見せてくれ。多分そこに書いてるだろ」
そんなことを修也が考えていると、彰彦が手を出してチケットを要求してきた。
「あぁ言われてみれば確かにそうか」
彰彦に言われて気づいた修也はチケットを取り出す。
「…………あぁうん、やっぱりあった」
彰彦は修也が取り出したチケットの隅にQRコードが書かれているのを見つけた。
「あっこれアレだろ、QRコード! 確か本当の名前は…………く……くぉ……」
同時に見ていた戒が声をあげるが、その声が段々しりすぼみになっていく。
「……忘れたのかよ霧生」
「まぁ一度聞いただけで覚えるというのは意外に難しいものだ。繰り返し学習することで本当の意味で身に付くのが一般的だ」
呆れたように呟く彰彦とフォローを入れる塔次。
「それじゃあ氷室先輩もその膨大な知識は繰り返し学習して身に付けたものなんですか?」
「何を言う。俺は一度聞いただけで大概は把握できる。難しいと言っただけで不可能とは言ってないぞ」
「…………えぇー……」
亜理紗の問いに対して事も無げに塔次は言い切る。
「いやぁそれは俺には無理だわ。スポーツなら一回やってみりゃコツ掴めるんだけどなぁ」
「いやそれはそれで大概おかしいからな? にしても何とも両極端な……」
戒は戒でおかしなことを言い出したので修也は突っ込みを入れる。
戒もスポーツ方面なら大概規格外である。
そういう意味では塔次と似通っているように思える。
「ある種の才能ってやつなんだろうなぁ。スゲェよなそういうの」
「何言ってるんですか。修也さんだって動体視力と反射神経が凄いじゃないですか」
「だな。球技大会で見せたアレはもはや神業の領域だろ」
そう呟く修也に今度は蒼芽と瑞音が突っ込みを入れてきた。
恐らく強引にランニングホームランを決めた時のことを言っているのだろう。
「そういう意味なら詩歌や彰彦だって負けてないわよ!」
そこに張り合うように爽香が割り込んでくる。
「え? 詩歌はまぁ料理ってことで分かるんだが……仁敷も?」
「ええ。『普通』ってことにおいて彰彦の右に出る人はいないわよ。彰彦は普通を極めに極めてるのよ!」
「あぁー……」
「おいちょっと待て爽香、普通を極めてるって何だ。そして何で納得するんだ土神」
爽香の説明を聞いて納得した修也に彰彦が待ったをかけてきた。
「いや、仁敷程普通を体現したやつはそうはいないぞ。霧生や氷室が尖りすぎてるってのもあるけど」
「……うん、アキ君は凄く普通だよ。だって、私ですら普通に話せるんだから……」
修也の言葉に詩歌も同調する。
確かに詩歌は一番の友達である蒼芽相手でも多少はどもるのに、彰彦だとそれすら無い。
幼馴染というのもあるだろうが、それ以上に彰彦は普通であるが故に親和性が高いのだ。
「確かになぁ。仁敷って何でも普通にこなすってイメージがあるわ」
「ふむ……何に対しても一定のボーダーラインを満たせるというのも一種の才能だな」
さらに戒と塔次も話に乗ってきた。
「ここまで来ると『普通』と言うより『万能』と言った方が良いかもしれんな」
「あぁー……確かにそっちの方がしっくりくる」
塔次の言葉に深く頷く戒。
「……何か自分が話題の中心になるって落ち着かないなぁ……」
「だろ? 俺の気持ちが少しは分かったか?」
「分かった分かった。だからさっさとボウリング場へ行こうぜ。場所はもう分かったから」
この話の間にもきっちりと情報を調べていた彰彦。
話を強引に纏めて目的地に向けて歩き出す。
修也たちはそれについていく形で移動を始めた。
「おぉー、ここがボウリング場か。やたらやかましい場所だなぁ……」
ボウリング場は駅から10分弱歩いた所にあった。
入ってすぐ修也の耳に入ってきたのはあちこちで勢いよくボールがピンにぶつかる音だった。
「まぁボウリング場ってそんなもんだ」
「仁敷は来たことあるのか?」
「まぁな。ここじゃなくてアミューズメントパークの方だけど」
「ああやっぱりあそこにもあるのか」
色々な遊戯施設を取り揃えているあそこならボウリング場もあっても何の不思議も無い。
「とりあえずここで立ってても仕方ないから受付を済ませよう」
「そうだな。受付は……あそこか」
修也は辺りを見回し、受付のカウンターらしきものを見つけたのでそこに足を進める。
「いらっしゃいませー。何名でのご利用ですか?」
修也が来たのを見て応対をする受付のお姉さん。
「えぇと……何人いるんだ?」
正確な人数を把握していなかった修也は一人ひとり指さし数えていく。
「………………13人か。改めて数えてみると多いなぁ」
つまりそれだけの人数が修也とそれなりの付き合いのある知り合いということになる。
他にもこの場にはいないが白峰さんや黒沢さん、陣野君や佐々木さんなども加えて良いだろう。
そんな間柄の知り合いが1人もいなかった引っ越し前とは比べ物にならない。
「では1レーン5名様までなので3レーンのご利用ということになります」
「あ、はい。で、このチケットってどこまで有効なんですか?」
そう言って修也は瀬里に貰ったチケットを受付のお姉さんに見せる。
「えぇと……これは1レーンのみに適用されます。なので申し訳ありませんが残り2レーンは利用料金を頂くことになります」
「まぁそりゃそうか。チケット1枚で無制限に無料になんてなるわけ無い無い。そんなチートアイテムみたいなものが存在してたまるか」
「修也さーん、あの永年フリーパスは……」
「あーあー聞こえない。何も聞こえなーい」
蒼芽の言葉にあえてスルーを決め込む修也。
「とりあえず残り2レーン分は全員で割り勘で良いよな?」
「ああ、問題無いぞ」
修也の問いに頷く彰彦。
他の面子も異論は無いようだ。
「と言うか土神君以外で割り勘でも良いんじゃない? 土神君はチケット出してくれてるんだし」
「いやこれ貰い物なんだけど」
「それでもチケットを出したのは土神という事実は変わらないだろう。そもそも13等分が12等分になったところで大して変わるまい」
「……まぁ、それもそうだけどさ」
爽香と塔次に諭され一応ではあるが修也は納得する。
「では代表者様のご署名をこちらにお願いします」
そう言ってお姉さんは1枚の紙を修也に差し出してきた。
「………………うん、これでよし」
「では確認させていただきます…………!? こ、これは……!」
修也が署名した受付用紙を確認したお姉さんの目が驚きで見開かれる。
「え?」
「も、申し訳ございませんが何か身分を確認できるものはございますか?」
「? あぁ学生なら学割が効くとかそういうアレか」
「あ、いえ、それもありますが……」
「?」
お姉さんの態度に疑問が残るが、学割が効くなら利用しない手は無い。
そう思い修也は学生証を取り出しお姉さんに提示する。
「これで良いですか?」
「や、やはり…………! すみません、少々お待ちください」
そう言ってお姉さんは慌ててスタッフルームに駆け込む。
「…………何だろう、何かデジャヴと嫌な予感が……」
「あ、あはは……」
「何かこんなことが前にもあったねー」
何となく覚えのある展開に修也と蒼芽は表情が引きつる。
それに対して由衣は大して気にした様子も見せずのほほんとしていた。
「……で、案の定という訳か……」
スタッフルームに通された修也たち。
目の前に現れた人物を見て修也はため息と共に呟く。
「ふふっ、来ちゃった」
「いやそんなサプライズで彼氏の家にやって来た遠距離恋愛中の彼女みたいなセリフ言われても」
そう修也は目の前にいるアミューズメントパークのオーナーに疲れ気味の声で突っ込む。
「はっはっは! やはり遊戯施設のオーナーたる者遊び心も十全に備えていないとね!」
「いやいらないと思いますよ? てか何でここに」
「ふふふ……僕がアミューズメントパークだけを経営しているといつから錯覚していたのかな?」
修也の質問に対して得意気に返すオーナー。
つまりこのボウリング場もオーナーが経営しているのだろう。
そして修也が来たら自分に連絡するように従業員に通達しているのだと思われる。
「にしたってわざわざ足を運んでこなくても」
いくら修也がアミューズメントパークでの事件を最小限の被害に抑えた恩人とは言えフットワークが軽すぎる。
オーナー業って意外と暇なのかと修也は訝しむ。
「おじさん久しぶりー! 相変わらずだねぇ」
「ご無沙汰しておりますおじ様。変わらずお元気なようで安心しました」
「おおっ、華穂ちゃんに美穂ちゃん! 大きくなったねぇ。今日は君たちもいるのか」
「あ……そうか、先輩と美穂さんは面識あるのか」
このオーナーは理事長と友人関係にある。
だったらその理事長の孫である華穂と美穂も顔見知りであっても何の不思議も無い。
「そちらのお嬢さん方も久しぶりだね。元気だったかな?」
オーナーが蒼芽と由衣の方を向いて聞いてくる。
「うんっ! 私はいつでも元気だよー!」
「あ、はい、おかげさまで。私たちのこと覚えていたんですか?」
「もちろん。職業柄人の顔を覚えるのは得意だからね」
聞き返す蒼芽に頷くオーナー。
「……で、わざわざ出向いてきて何の用だったんですか? ただ挨拶しに来たってわけじゃないんでしょう?」
「おお、察しが良いねぇ土神君。君たち今日はここに遊びに来たんだろう? でもその人数だと1レーンには収まりきらないんじゃないかな」
「えぇまぁ3レーン使うつもりです。でも全員で均等に割れば大した金額にならないしそもそも1レーン分は無料チケットがあるので」
「よし、じゃあその残り2レーン使用料は僕が払おう!」
「えっ!?」
オーナーの出した提案に修也は驚く。
「どうだいこれくらいなら君も気兼ねしないだろう?」
「いやでも……そんなことまでしてもらう大義名分はもう無いんですが」
ハンマー男の事件の礼はフリーパスで完結しているし、何なら先日のプールでの食事代を出して貰っている。
そこから更に今回のレーン利用料まで出して貰うのはいくら何でも貰いすぎだと修也は思うのだが……
「いやそうでもないよ? ここ最近、ウチに『無給で良いから働かせてくれ!』っていう若い男がたくさんやって来ててね。訳を聞けば君の恩に報いるために町に貢献したいって言うんだよ」
「え、えぇ……」
「流石に無給って訳にはいかないからアルバイトと同じ時給は出してるけど皆凄く真面目に働いてくれてね、良い労働力を確保できたのさ。これはそのお礼だよ」
オーナーの言葉に何も言えない修也。
間違いなく猪瀬の元部下たちだろう。
「まぁそういう訳だ、気にせず楽しんでいってくれたまえ!」
そう言って豪快に笑いながらスタッフルームを後にするオーナーを修也は呆然と見送ることしかできなかった。
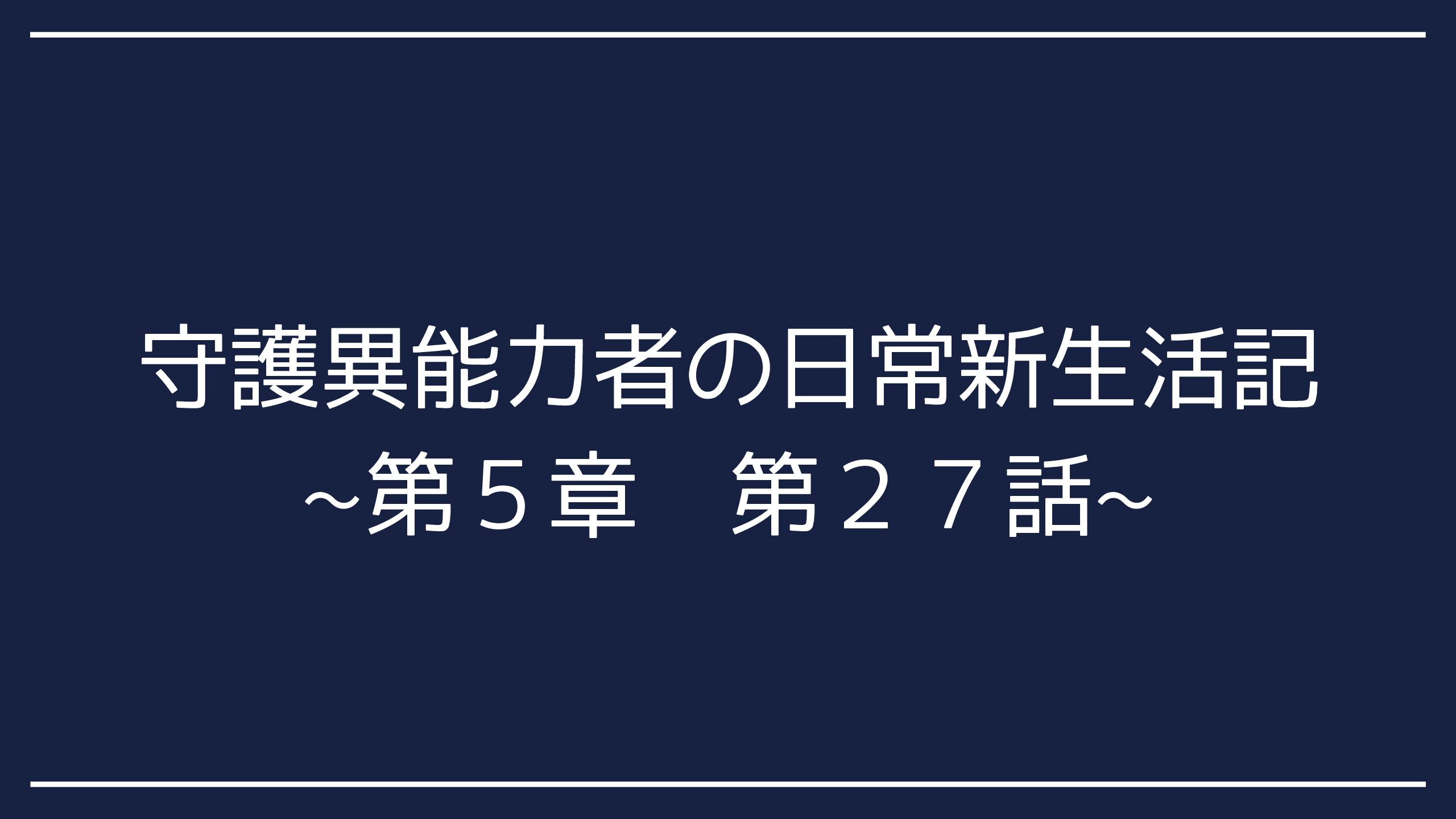

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]