「ほら見なさい、私の言った通りだったじゃないのよ」
「いやだから、たとえそうだとしてもやらないわけにはいかないんだってば」
ドヤ顔でふんぞり返る爽香を彰彦が窘める。
結局5回は表も裏も三者凡退であっさり終わってしまい、2-Cと2-Eの試合は引き分けとなったのだ。
2-Cは瑞音の剛球を最後まで攻略できず、2-Eは守備位置を元に戻した2-Cの守りを突破できなかった形だ。
「しかし最後の試合が引き分けかぁー……何か締まらねぇな」
「まぁそういうこともあるんじゃねぇの?」
ちょっと不満げな戒に対して修也は泰然としている。
「だったら霧生、こういうのはどうだ?」
そこに瑞音がやってきて提案を出してきた。
「私とお前で全力の三球勝負をやるんだ」
「三球勝負?」
「ああ、試合中の時のようなわざとタイミングをずらしたりしない、本当の意味での全力だ。もちろん試合外での勝負だからチームの勝ち負けには影響しない。いわゆるエキシビションマッチってやつだな」
「お、何か面白そうだな! エキシ何とかって意味はよく分からんけど」
「……エキシビションマッチだ。勝敗よりも技術の披露や観客を楽しませることを目的とした試合のことを言う」
言葉の意味をよく分かっていない戒に塔次が注釈を入れる。
「しかしそれだとそろそろ霧生はホームラン打ちそうなんじゃね? 実際試合中も結構いい当たり出してたし」
確かに戎はあの瑞音の剛球にも力負けしていなかった。
そして試合中のようにタイミングをずらす戦法をとらないのであれば今度こそホームランになってもおかしくない。
「言ったろ? 本当の意味での全力勝負だって。だから私も本気で投げる」
「え、あれ本気じゃなかったのかよ?」
瑞音の返事を聞いて修也は少し表情が引きつる。
ハンパない球威で修也と戒以外にはかすりすらさせなかったあの剛球が実は本気ではなかったらしい。
「じゃあ何で試合中本気で投げなかったんだ? お前そういうのに手を抜くタイプじゃないだろ?」
瑞音は常に全力でぶつかってくるタイプだと修也は思っていた。
だからそんな疑問が湧いたので聞いてみる。
「…………俺の手がもちそうになかったからだよ……」
「え?」
修也の疑問に別の声が答えてきた。
声の方を見るとそこにいたのは2-Eのキャッチャーをしていた生徒だ。
グローブを付けていた左手が赤くなっており、氷水の入ったビニール袋を当てて冷やしている。
「真芯で捕らないからそうなるんだよ。ちゃんと捕ればどうということはねぇよ」
「いや無茶言うなよ!?」
「……とまぁそういう訳でちょっと加減してたんだ」
「あー……大変だったなぁ」
ちょっと涙目になっている2-Eのキャッチャーを労う修也。
「だから土神にキャッチャーをやってもらう。それなら私も全力で投げられるからな」
「え、ちょっと待って意味が全然分からん」
突然意味の分からないことを言い出した瑞音に修也は待ったをかけるのであった。
守護異能力者の日常新生活記
~第5章 第15話~
「さっきも言ったがこれはエキシビションマッチみたいなものだからな。絶対に2-Eから選出しないといけない訳でもないだろ」
「だからって何で俺なんだ」
迷い無く言ってのける瑞音に修也は当然の質問をぶつける。
「それはお前は私が見込んだ男だからだ!」
「理由になってねぇよ」
「いやそうでもないぞ。相川が見込んだってことはそれなりの力量があるってことだからな」
瑞音の持ち出した理由を切って捨てようとした修也だが、それを戒に否定されてしまう。
「バレーボールの時だってそうじゃねぇか。私がどんなスピードで打ち込んでも全部打ち返してきただろ」
「あぁ、私も遠目ですが見ましたよ。流石修也さんだなぁと思って見てました」
瑞音の言葉に蒼芽が追随する。
「いやあれは条件反射であってだな……」
「つまり無意識でできるってことだろ? なら尚の事適任じゃねぇか」
何とか弁明を試みた修也だが、どうやら逆効果だったらしい。
「ま、物は試しだ。実際やってみりゃ良いだろ」
そう言って瑞音は修也にグローブを手渡す。
「はぁ……期待に応えられなくても文句言うなよ?」
修也はため息を吐きながらキャッチャー所定の位置まで歩いて行く。
「それは無いな。土神は毎回私の期待以上の動きをしてくれるからな」
マウンド上で肩を回しながらそう言う瑞音。
「……相川に限らず何なんだろうな、この俺への信頼感の高さは……」
瑞音だけでなく蒼芽や詩歌、華穂や由衣も修也に多大な信頼感を寄せているし、2-Cや1-Cの生徒たちも修也のことを高く評価している。
未だに修也はその感覚に慣れていない。
「んじゃまぁ、最初は投球練習だ」
そう言って瑞音は軽く球を投げる。
それでも軌道は放物線ではなくほぼ直線を描いている。
「っ」
修也はそれを正面で捕らえる。
ボールがグローブに収まった瞬間、『スパァンッ!!』と乾いた小気味良い音が辺りに響き渡る。
「これで練習の肩慣らしとか……お前の肩はどうなってるんだ」
「そう言うお前こそ綺麗に真芯で捕らえてるじゃねぇか」
修也が投げ返したボールを受けながら瑞音は楽しそうに笑いながら言う。
(……あ、何か嫌な予感)
何度か身に覚えのあるパターンがやってきたことに修也は一抹の不安を覚える。
「ほらもう1球行くぜ!」
そう言って瑞音はさっきよりも強い球を投げる。
それも修也は真芯で捕らえて辺りに快音を響き渡らせる。
そのことに観客席からもざわざわとどよめきが起き始めた。
「すっげぇ良い音出てるなぁ……キャッチボールってあんな良い音出るもんなのか?」
「俺の時はあんな音出なかった……真芯で捕ったらああなるのか?」
「にしても土神君、表情が全く変わらないわね。ちゃんと捕れば痛くも何ともないってこと?」
「流石土神先輩だ!!」
そんな声が聞こえ始める。
「……いやキャッチボールひとつで大袈裟な」
どれだけ速かろうが所詮は人の手で投げられたものだ。
拳銃の弾道すら見切れる修也としては別に慌てるようなものではない。
「そのキャッチボールひとつとってもお前の凄さがにじみ出てくるってこったろ」
「……それこそ大袈裟な」
そう言いながら投げる瑞音の球はどんどん勢いを増していく。
それでも修也は顔色ひとつ変えずキャッチする。
その音も段々重みが増していき、瑞音の球威の高さを知らせている。
「ほらどんどんギア上げてくぜ! どこまで行けるか楽しみだ!」
「おい本題を忘れるな! これ肩慣らしの投球練習だろうが!!」
本来の目的を忘れてエキサイトしだした瑞音を修也は慌てて止める。
瑞音は一度ハマりだすと熱中する癖がある。
修也が止めなかったらひたすらにキャッチボールを続けることになっていただろう。
「…………あ、そうだったな。ということで待たせたな霧生」
「お、もう良いのか?」
瑞音が誤魔化すかのように戒に声をかける。
呼ばれた戒はバットを持ってバッターボックスに立った。
「さっきも言ったがこれは小細工の無い全力勝負だ。私は全力で投げる。だからお前も全力で来い!」
「おう、望む所だ!!」
そう言い合ってお互い構える瑞音と戒。
「じゃあ行くぜ!!」
掛け声と共に瑞音が第1球を投げる。
「!!」
瑞音の手から放たれた球は、ほぼ一瞬で修也のグローブに収まった。
その時響いた音はまるで大砲を撃ったかのようだ。
「おいおいなんて球投げるんだよホントに……」
修也は呆れながら呟く。
「……やっぱり私の見立てた通りだ。土神、お前なら私の全力でも難なく受け止められたな」
「あれ、これ霧生との勝負だよな? なんで焦点が俺に来てる訳?」
瑞音が楽しそうに口元を歪めているのを見て突っ込む修也。
「なるほど、良い球を投げるじゃねぇか相川!」
一方で戒はそんな瑞音の球を見ても臆することなくこちらも楽しそうに軽く笑っている。
「やっぱ勝負ってのは持てる力を全て出してぶつかるのに限るな!」
「あぁ、同感だ!」
「…………まぁ分からんでもないけど俺のいない所でやってほしいなぁー……」
お互い視線をぶつけ合い火花を散らす戒と瑞音。
それを修也は少し離れた視点で見ながら呟く。
「ふんっ!」
「オラァッ!!」
続けて放たれた第2球を戒は迎えうつ。
ただ、当たりはしたものの真芯ではなかったようで打球はファールグラウンドを突き抜けた。
「……2球で当ててくるか! やっぱスポーツに関しては天才的な超人レベルだなお前は」
打球を目だけで追いながら瑞音がそう言う。
「ふふんっ! まーな!!」
瑞音の言葉に戒は自慢気に鼻を鳴らす。
「……うん、スポーツ『は』天才的なんだよ、スポーツは」
「まぁ誰にでもひとつくらいは自慢できるものがあるってことね」
「今の時代、一芸に秀でているというのは十分な強みだ。せめてもの救いがあって良かったではないか」
「お前ら褒めるのか貶すのかどっちかにしてくれよ!!」
観客席で見ている彰彦たちの褒めているのかどうかよく分からない言葉に戒は突っかかっていく。
「……いやまぁ、氷室の言う通り何かひとつ絶対の自信を持てるものがあるって言うのは良いことだと俺も思うぞ?」
「え? そ、そうか?」
修也の言葉に満更でもなさそうな表情の戒。
「そういうのって自己肯定感に繋がるからな。俺には無いから羨ましいよ」
「いやいや土神にだってあるだろ。俺や相川ですら崩せないその守りの固い護身術とか」
「そんなのが何の役にも立たない、何の自慢にもならない世界の方が良いに決まってんじゃないか」
「うーん……まぁそれはそうだな……」
修也の『力』を含めた身を守る能力が日の目を見るということは、それだけ身の回りに危険が迫っているということでもある。
身に付けておいて損はないが、そんなものを使う機会が無いに越したことは無い。
「……でもさ、だからと言ってお前のその能力そのものを否定して良い理由にはならないと思うぜ」
「え」
しかし続けて出てきた戒の言葉に修也は一瞬虚を突かれた。
「長年かけて身に付けたことまで否定するなってことだ。俺は難しいことはよく分かんないけどよ、努力と経験は絶対に無駄にならないと信じてる」
「…………」
「自分は絶対に自分を裏切らない。だからせめて自分だけでも自分を信じてやれよ」
「おー、良いこと言うじゃねぇか霧生にしては」
修也と戒の話を聞いていた瑞音が会話に混ざってくる。
「まぁ土神の言う通り危険から身を守る必要の無い世界の方が良いってのは間違っちゃいないが、何があるか分からん世の中だからな。あって困ることは無いだろ」
「……『転ばぬ先の杖』ってやつか」
「そうそうそういうこった」
「…………? 何で急に杖の話になったんだ?」
「…………」
「…………」
修也の呟きに対して瑞音は頷くが、戒は首を傾げて疑問顔だ。
どうやら戒は『転ばぬ先の杖』ということわざを知らなかったようだ。
そのことに修也と瑞音は気勢を削がれてしまった。
「…………とりあえずラスト1球行くか」
「…………あぁ、そうだな」
微妙に白けてしまい、修也と瑞音は何とも言えない気の抜けた状態で構え直す。
「おぉいどうしたんだよ? 答えてくれよ土神ー、相川ー」
「後で氷室あたりにでも聞け……とりあえずお前は目の前のことに集中しろ」
そう言って無理やり話を打ち切る修也。
「それもそうだな。よーし来い、相川!!」
「……ふぅーっ…………泣いても笑ってもこれが最後だ。行くぜ!!」
瑞音は半ば無理やり気を取り直し、大きく息を吐いて表情を引き締める。
「うぉらぁっ!!」
瑞音の渾身のストレートが放たれる。
それは今までの投球の中で一番速く球威のあるものだった。
「ぬぉりゃああぁぁぁ!!」
それに戒も全力で迎えうつ。
戒がフルスイングしたバットは瑞音の投げた球を捉え、弾き返してまっすぐ飛んで行く。
そしてそのままホームラン…………まではいかず、センターの定位置から少し後ろに下がったところあたりで落ちた。
「あークソ、打たれちまったかー!」
「あークソ、ホームランまではいかなかったかー!」
そう言ってお互い悔しさをにじませる瑞音と戒。
「でもスッキリした! やっぱ全力でのぶつかり合いは良いもんだな!」
「そうだな、正々堂々全力でぶつかれば勝っても負けても後腐れ無いもんな!」
でも次の瞬間には実に晴れ晴れとした表情で笑い合う。
そんな二人に観客席から拍手と歓声が沸きだす。
「凄いね相川さん! 全力ならあんなに速い球投げられるんだ!」
「とても高校の球技大会とは思えないハイレベルだったよ!!」
「ソフト部に誘えないのが悔しい! 絶対エースになれるのに!!」
「そんな球をあそこまで飛ばせる霧生もスゲェな!」
「あれでも野球の経験自体は無いんでしょ? まさしく超人級じゃん!」
「いやあの二人も凄いけどやっぱり一番凄いのは土神君でしょ!」
「だよな! あの超スピードの投球にも顔色ひとつ変えず捕球してるし」
「土神ならあの全力投球でも余裕で打ち返すんじゃね?」
「やっぱり土神先輩は凄い人だね!」
「いやだから何でそうなるの!?」
途中から再び自分を称賛する声に変わりだしたことに突っ込みを入れる修也。
「あ、あはは……まぁ修也さんですから……」
「えっと、その……先輩は凄い人だというのが……その……既に共通認識なのかと……」
「まぁ確かに土神くんは凄い人ってのは学校全体に知れ渡ってる感じだよねぇ」
「やっぱりおにーさんは凄い人なんだよー!」
「えぇー…………」
蒼芽たちの言葉で自分の立場を改めて認識した修也。
呆れて言葉も無くがっくりと肩を落とすのであった。
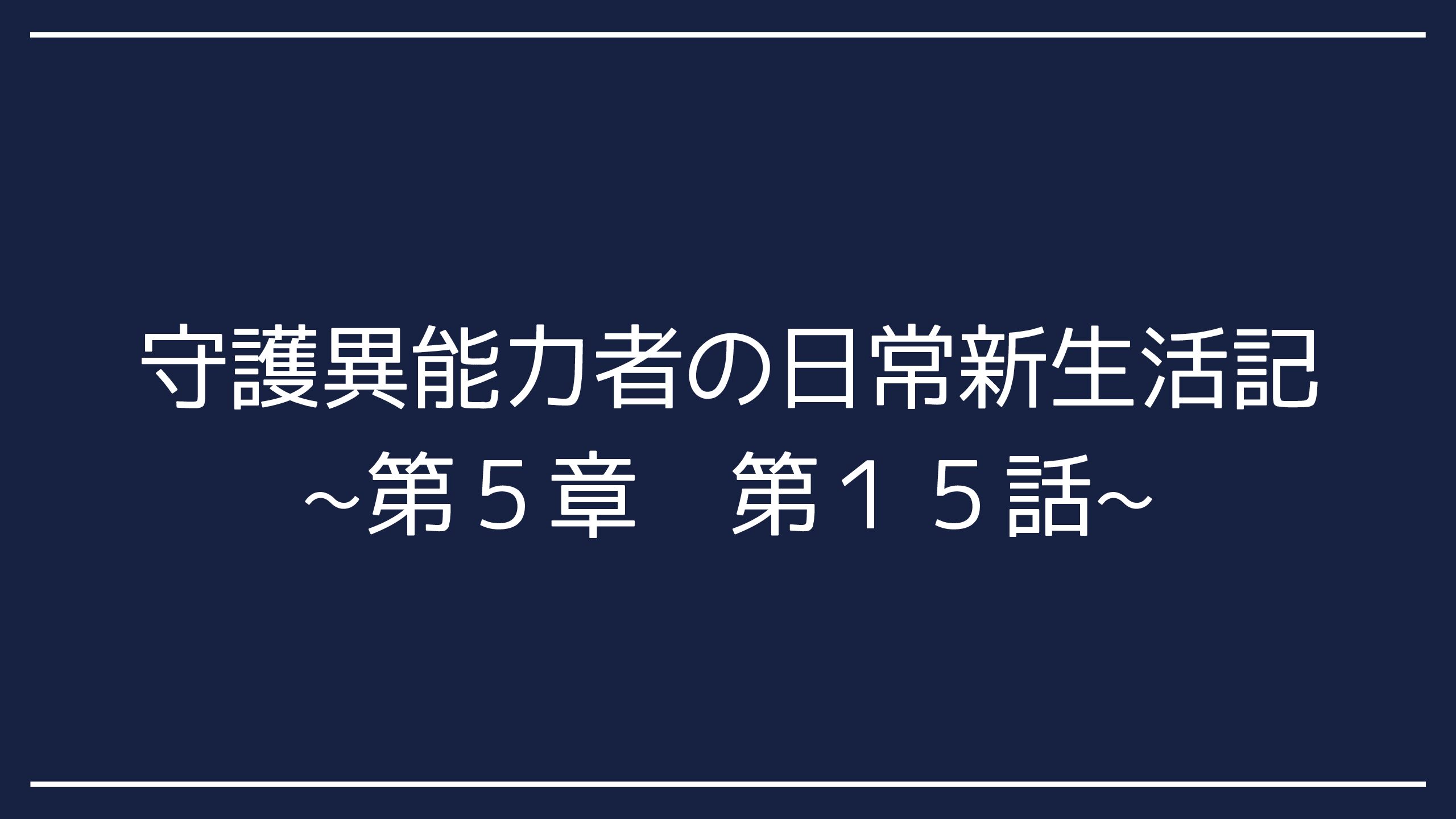

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]