話は少し遡り、帰りのホームルーム直後。
陣野君と佐々木さんへのお祝いムードの陰に隠れて詩歌はこっそりと教室を後にした。
いつまでも教室に残っていると、いつ自分の方に話の矛先が向いてくるか分からない。
修也と多少なりとも関係があると知られている以上、『いつ』かは分からないが、『いつか』は必ず来る。
その『いつか』が来る前に早々に退散することにしたのだ。
「ふぅ……なんだか、今日は疲れちゃった……」
教室から少し離れた後、詩歌はそっとため息を吐いた。
今朝突然姉の爽香から、修也と一緒に昼食を食べると言われ、朝から落ち着かない気分で授業を受けた。
昼は修也が来る前も来てからも、緊張と不安で心臓が爆発するのではないかと思うほどだった。
しかも成り行きで下の名前で呼ばれることになってしまい、もう緊張が臨界点を突破して気絶しそうにまでなっていた。
さらに昼食を終えて教室に帰ってきたらクラスメートから修也に関する質問責め。
これは蒼芽が矢面に立ってくれたが、それでも目を回してしまい何もできなかった。
その後は陣野君と佐々木さんの方に話題の中心が移ってくれたおかげで事なきを得たが……
一度に大量のイベントが押し寄せすぎて、詩歌は精神的にかなり疲労してしまっていた。
(こういう時は……何もせずまっすぐ帰って、早く休もう……)
そして自分の部屋で新しい料理のレシピでも考えよう。
そう思い詩歌は校舎入り口へ向かう。
「あっ……」
その途中で詩歌は知ってる人物の背中を見つけた。
基本的に詩歌は人見知りが強く、さらに引っ込み思案なので自分から声をかけるということはできない。
ただ、それにも例外はある。
今見つけた人物はその例外だ。
「アキ君」
詩歌はその例外の人物、彰彦に声をかける。
「ん? おっ、詩歌じゃないか。今帰りか?」
「うん。アキ君も?」
「まぁな。……ところでどうした詩歌?」
「えっ……何が?」
「やたら疲れてるように見えるぞ?」
流石長年幼馴染をしているだけあって、彰彦は一目見ただけで今の詩歌の状態を見抜いたようだ。
「あ……うん、ちょっと……色々あって……」
今更彰彦に取り繕う意味も無いので、詩歌は普通に頷く。
「ああ……昼のアレか」
「その前後でも、色々と……」
「ん? 『前』は分かるけど、『後』? 昼からも何かあったのか?」
昼までなら、爽香が何か面倒ごとを企ててそれに巻き込まれたんだろうと想像はつく。
しかし昼からは特に何もなかったはずだ。爽香の様子も特にいつもと変わりは無かった。
気になった彰彦は詩歌に聞いてみる。
「えっとね、実は……」
彰彦に促され、詩歌は昼食が終わった後起きたことを話し始めた。
守護異能力者の日常新生活記
~第2章 第12話~
「えぇ……後半土神関係無いだろ……」
「やっぱり……アキ君も、そう思う……?」
詩歌から一通りの話を聞いた彰彦はげんなりとした表情で呟いた。詩歌もそれに同調する。
「とりあえず、その陣野君と佐々木さん? はおめでとうと言っておくべきか……」
「ま、まぁ……うん……」
「でも聞いた限りでは、多分陣野君の方は少なくとも最初は告白の意図は無かったと思うぞ」
「えっ……?」
彰彦の言葉に意外そうな顔をする詩歌。
「ど、どうして……?」
「たとえばだ。詩歌が注文した食事が想像以上に多くて食べられなくて困ってたとする」
「う、うん……」
「そこにちょっと気になるなー……ってクラスメートがやってきて……」
「えっ……そ、そんな人いないよぅ……」
「あー、たとえだたとえ。深く考えないで良い」
「あ……う、うん……」
「で、そのクラスメートが『それ、食べ切れないなら頂戴!』……って言ってきたらどう思う?」
「え……そ、それはちょっと……」
彰彦のたとえ話に、嫌そうな表情をして首を振る詩歌。
「だろう? 普通ならドン引き案件だ。気になってる子へのアプローチ方法としては最悪だな」
「じ、じゃあ……どうして……陣野君は、そんなことを……?」
「ここからは想像だが、陣野君はシンプルにたくさん食べたかっただけなんだろう」
「あ……そう言えば、『大きくなるためにいっぱい食べたい』って……」
「それは良いけど普通に大盛り頼めば良いじゃないかよ……」
「た、多分……それは、佐々木さんが、食べ切れなくて残しちゃうって言ったから……」
「それは仕方ないけど普通に減らして頼めば良いじゃないかよ……」
「あ、そう言えば……」
この学校の学食は、量をある程度は任意に調整することができる。
流石に戎程のアホな量ともなるとそうもいかないが、陣野君や佐々木さんのような小柄な学生の調整量などたかが知れている。
量を調整しても値段は変わらないので佐々木さんは損をすることになるが、そんなもの微々たるものだろう。
「これも想像だが、これは佐々木さんの策略じゃないか?」
「……え?」
彰彦の推測に、詩歌は不思議そうな顔をする。
「策略……つまり、佐々木さんは狙ってあの状況を作ったってこと……?」
「ああ。話から察するに、佐々木さんは陣野君に気があったわけだろ?」
「た、多分ね……」
「となると、陣野君が体が小さいことが悩みの種で、『いっぱい食べて大きくなりたい』と常日頃思っているということを知っていても不思議じゃない」
「そ、そうだね……」
「だったら、土神が唐揚げ定食を食べたから明日自分たちも同じものを食べたい……って、よく考えたらこれも意味不明だな」
「うん……意味が分からないよ……」
意味不明な1ーCのミーハー根性に眉根を寄せる彰彦。
詩歌も同調して頷く。
「まぁ良いや、それは置いとこう。で、その話の流れに乗って自分も唐揚げ定食を頼もうとする。でも多くて食べ切れないかも……と言って困って見せる」
「何でそんなことを……」
「陣野君の気を引くためだ。あとは陣野君が食いついてくるのを待てばいい」
「食いついてこなかったり、他の人が来たらどうするの……?」
「その時は普通に量を減らして注文するんじゃないか? それにさっきも言ったけど、残り物を貰おうとするのは普通はドン引き案件だ。高確率で他の人は来ないだろう」
「……とすると、佐々木さんは、陣野君だけが食いついてくると分かってたからそんな事を……?」
「陣野君の性格その他を把握してたとしたらあり得ない話ではないな」
「えぇ…………何か、全部台無しだよ、アキ君……」
「俺に言うなよ。しかもこれは全部想像だ。真実は違うかもしれないぞ?」
「う、うん……」
「……でもまぁ、真実ってのは時には残酷なものなんだけどな」
「……やっぱり台無しだよ、アキ君……」
彰彦の話に複雑な表情を浮かべる詩歌。
やはり年頃の女の子としてはもうちょっとメルヘンチックな話を期待したかったというのが本音だ。
しかし蓋を開けてみればなんだかメンヘラチックな話だったのだから無理もないだろう。
「だから想像だよ想像。もしかしたら、陣野君も佐々木さんに気があって、チャンスだと思ったけどテンパってそんな行動に出た可能性だってあるさ」
「そ、そうだね……そっちの方が良いな……。悪い顔して『計画通り……!』とか言って笑う佐々木さんとか想像したくないよ……」
「確かにそれは嫌だな。どんな子か知らんけど」
と、その時、どこからか何かが振動する様な低い音が響いた。
「アキ君、携帯鳴ってるよ……?」
それがスマホのバイブ音だと気付いた詩歌が指摘する。
「あ、ホントだ」
詩歌の指摘で自分に通知が来た事に気付いた彰彦がスマホを取り出す。
「えっと…………あー、爽香からだ」
「あ、そう言えば……お姉ちゃんと一緒じゃなかったんだね……」
「そりゃ四六時中一緒にいる訳じゃないし」
「え…………」
彰彦の言葉に意外そうな顔をする詩歌。
「……なんで意外そうな顔をする」
「……だって、実際意外だったから……」
「……オイ」
「じ、冗談だよぅ……」
ジト目で睨む彰彦に対し、そう言ってクスクス笑う詩歌。
彰彦相手だとこう言う冗談も言えるし、笑う事もできるようだ。
「全く……で、話を戻して、爽香のやつ何か最近ひとりで町を散策して面白そうな店とか探すのにハマってるんだよ」
「あ、そうなんだね……」
「……で、見つけたらこうやって通知で呼び出される訳だ」
「た、大変だね……でも……それって、お姉ちゃんがアキ君とデートする場所を頑張って探して、見つけたら一緒に楽しみたいってことじゃ、ないかな……?」
「…………あー……確かにそう言う解釈もできる、か……」
「お姉ちゃんは……なんだかんだ言っても、相手の事を……ちゃんと考えてくれてる、から……」
「……そうだな」
「じゃあアキ君、頑張って……ね?」
「そこは『頑張って』なのかよ……全部台無しだよ」
それは普通なら彼女からのデートのお誘いに行く人に使う言葉ではない。
しかしあえてその言葉を使う詩歌に彰彦はため息を吐く。
「さっきのお返しだよ。それに……お姉ちゃんだし……」
「はぁ……じゃあ行ってくる。詩歌も気を付けて帰れよー」
そう言って彰彦は今来た道を引き返していった。
「………………」
詩歌はその背中を見送りながらしばらくの間何かを考えた後、くるりと振り返り帰り道を一人で歩いていった。
「………………うーん……」
その日の晩、詩歌は自分の部屋でベッドに腰かけながら何かを考えていた。
「詩歌ー、お風呂空いたわよ……って、どうしたのそんな中途半端な姿勢で」
そこに爽香が部屋に入ってきた。
風呂から出た直後なので、髪が少し濡れている。
「お姉ちゃん……え? ち、中途半端……かな?」
爽香に指摘され、自分の体勢を見直す詩歌だが、別にどこもおかしなところは無い気がする。
「座るなら椅子に、ベッドなら寝転がってなさいよ」
「えぇ……」
爽香の理不尽な物言いに閉口する詩歌。
「で、何考えてたの? どうやったら土神君に振り向いて貰えるか、とか?」
「なっ……なななななな、そ、そんな事、か、考えてない、よ……!?」
「メチャクチャ動揺してるけどね」
「そ、それは……お姉ちゃんが急に変な事言うから……!」
「あながち見当はずれでも無いと思うんだけどねぇ……」
「ほ、本当に、違うから……!」
「既に一緒に住んでる舞原さんっていう超強力なライバルがいるんだから……」
「ま、舞原さんは友達、だよ……! そ、それに、本当の本当に違うから……!」
「じゃあ何考えてたのよ?」
さらりと話題を戻す爽香。
どうやらただ揶揄っていただけらしい。
「えっ……えっと、お姉ちゃん、携帯電話って便利?」
「へ? 携帯?」
全く予想していなかった質問に意外そうな声をあげる爽香。
「ああ、そう言えば詩歌はまだ携帯持ってなかったわね」
「う、うん……私には使う機会なんて無さそうだったから……高校に入った時に買ってくれるって言うのを断ったけど……」
「それなのに持とうとしようと思ったって事は、何か心変わりするきっかけでもあったの?」
「……友達が、できたから……必要な時に、連絡が取れるかなって……」
「まぁ、あったら便利なのは間違いないわね」
「でも……難しそうだから、やっぱりやめといた方が良いかな……って、迷ってて……」
「あー……また詩歌の悪い癖が出たわね」
どうしようか迷う詩歌の姿を見て、ため息を吐きながら爽香がぼやく。
「……え?」
「詩歌、あなたはやる前からあれこれ悩みすぎなのよ。そしてネガティブな面ばかり見て、やる前から諦める」
「そ、そんなことは……」
「あるでしょ。現に今だって『難しそうだから』ってだけでやめようとしてる」
「う……」
「料理だけはどんなに難しそうでも絶対に諦めないんだから、他も同じようにすればいいのに」
爽香が指摘する通り、詩歌は料理に関してだけは絶対に妥協しないし諦めない。
材料が調達できないなどどうしようもない理由ならともかく、手間暇がかかるとか火加減が難しいなどの理由くらいでは詩歌の料理への情熱は止まらないのだ。
一例として、今では大根の桂剥きを最初から最後まで一切途切れさせず、しかも向こうが見えるくらいの薄さを均一に保つことができるまでになっている。
玉ねぎのみじん切りは1玉を1分以内でやってのける。
卵を片手で割ることなど、詩歌にとっては朝飯前だ。
「ホント、詩歌は料理に関しては超人級よね……」
「そ、そんなことは……好きだからやってるだけだし……」
「まぁそれは置いといて、まずはとりあえずやってみたら良いのよ。全部を覚える必要は無い。ひとつずつ機能を覚えれば良いの」
「そ……そう、なの?」
「私だって今の携帯をフルに使いこなせてるとは思わないわよ。でもそんなもんよ」
「そ、そうなんだ……」
「ま、カタログ見せてあげるからそこから選んでみなさい。分からない所があったら教えてあげるから」
「う、うん……ありがとう、お姉ちゃん」
やはりなんだかんだ言っても爽香は面倒見が良い。
だからこそ振り回されつつも姉妹仲が良いのだろう。
「あと、お父さんとお母さんにもちゃんと話しておいた方が良いわね」
「あ……そうだね。じゃあ、お風呂の後にでも話すことにするよ……」
「じゃあカタログ出しておくから、お風呂から出たらリビングに来なさい」
「うん」
話が纏まったところで、爽香は詩歌の部屋を後にする。
詩歌も着替えを持って部屋を後にして風呂場へ向かうのであった。
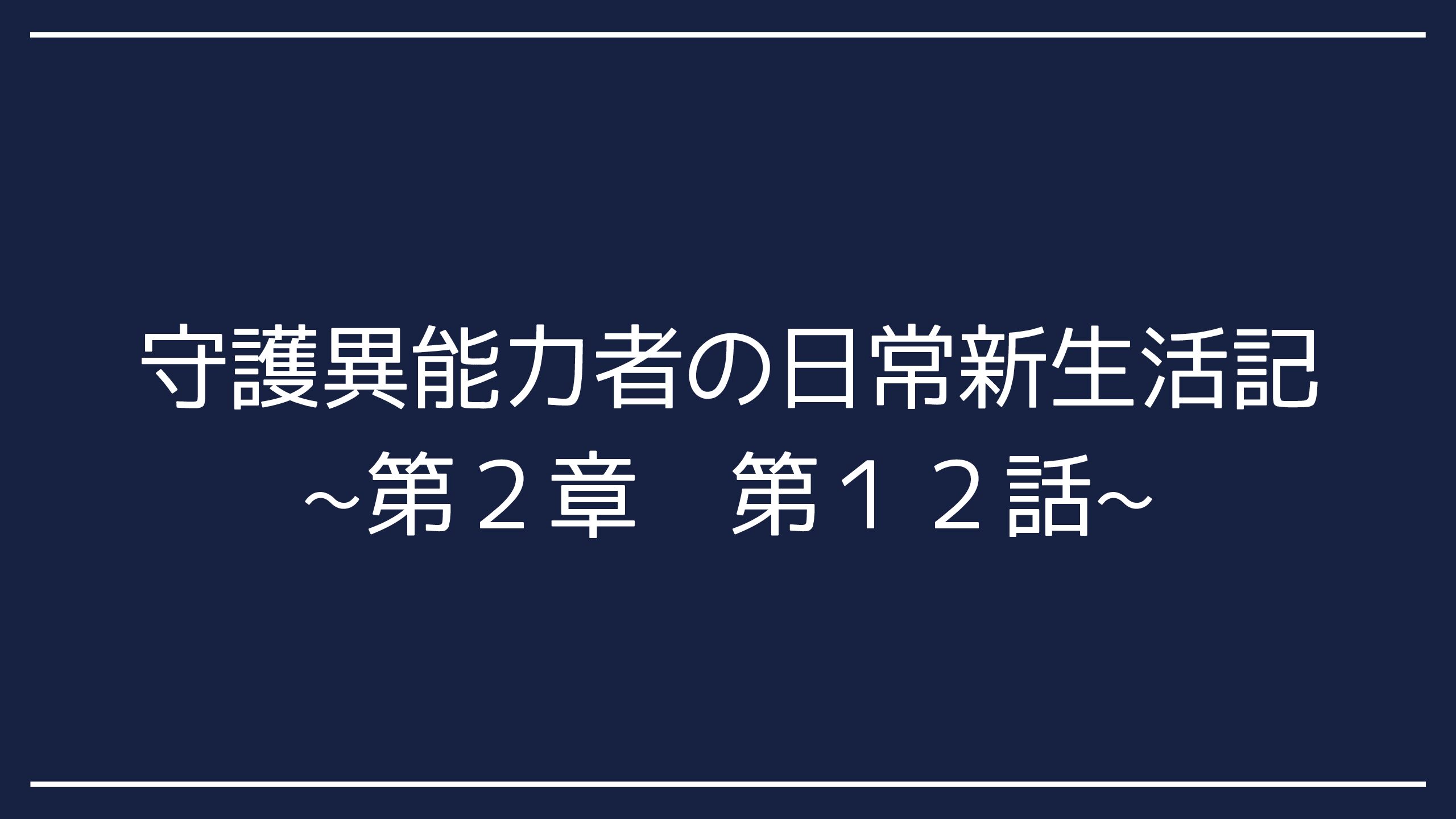

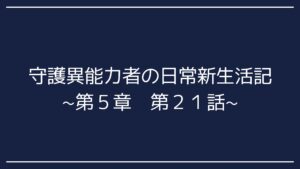
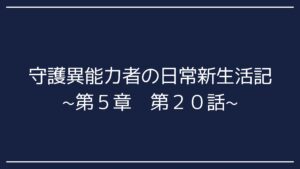
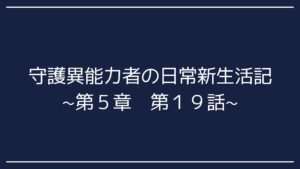
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]