「ほら、見えてきたわよ。あれが入り口」
爽香が指さした先には、確かに遊園地などによくある入場券売り場のような建物があった。
「いや近いな!? 駅出てまだ5分も経ってないぞ?」
想像してたよりもずっと早く目的地が見えてきたことに修也は驚く。
修也はもう少し歩くものだと思っていた。
いくら何でも駅から出てすぐ目的地があるなんて思いもしなかったからだ。
しかし蓋を開けてみれば、駅から出て少し歩いただけで入り口が見えてくるという、あり得ないほどスムーズなアクセスだった。
「あえて駅近くにしたらしいわよ。気軽に行くことができるようにって」
「にしたって限度があるだろう……これ駅が後からできたって言っても信じられるレベルだな……」
呆れと感心が入り混じった声で呟く修也。
「……それ、あながち間違いじゃないかもしれないぞ?」
「え?」
修也の呟きに彰彦が答える。
まさか真面目に受け止められるとは思っておらず、修也は気の抜けた返事をしてしまった。
「ほら、ここってこの施設以外はコンビニしか無いだろ?」
「ああ、昨日爽香がそんな事言ってたな」
「と言うことは、駅が先にできてたとしたら……」
「……利用価値ゼロじゃねぇか」
何が悲しくてコンビニしか無いような駅で降りなければならないのか。
というか、その場合そもそもこのコンビニも存在意義が微妙である。
それに、コンビニしかないのであれば、乗ってくる客も見込めない。
だとすると、この施設ができたからアクセスを考えて後から駅を作ったか、もしくは駅も同時に作ったと考える方が自然である。
「しかしそれだと、駅ひとつ作れる資産家って何なんだよって話になるが……」
「まぁここ私鉄だし、不可能じゃないんじゃない? 知らないけど。それよりも早く行きましょ」
爽香がどうでも良さそうに言って話を締める。
見ると開場時間は過ぎているらしく、次々と人が流れて入り口から中へ入っていく。
「ご、ごめんなさい……私のせいで、遅れちゃって……開場時間に、間に合わなくて……」
その様子を見た詩歌が申し訳なさそうに頭を下げて修也たちに謝罪する。
「いや別に詩歌のせいってわけじゃないだろ」
「そうそう。それに別に開場時間前に並んでなきゃならないってわけじゃないし」
「それにたとえ開場時間前に着いたって、チケット買うのに並んで待たなきゃならなかったんだから大して時間は変わらないわよ」
そんな詩歌に対して修也・彰彦・爽香はそれぞれ気にしてない意思を見せてフォローする。
「確かに今なら人が流れてるからチケットも大して並ばず買えるな」
「そういうこと」
「それにしても、さっきの電車の混み具合から考えたらもっと並んでてもおかしくないと思うんだけどなぁ」
「年間フリーパスとか持ってる人はチケット買わずに入れるからな」
「そんなのもあるのか……」
「それに混雑回避の為に入り口はかなり大きく作られてるのよ。だから入場処理もかなりスムーズよ」
「へぇー、結構色々考えてあるんだなぁ」
爽香の言葉に感心しながら、修也たちは入場チケットを買うために列に並び始めた。
守護異能力者の日常新生活記
~第2章 第23話~
「……でもまぁ、行列の流れること流れること」
列に並んだものの、全くと言って良いほど立ち止まることなく修也たちはカウンターにまで辿り着くことができた。
「いらっしゃいませー。何名様ですか?」
カウンターの向こう側に座っているキャストのお姉さんが応対してくれる。
「高校生4人です」
「高校生ですね。学生証はお持ちですか?」
「はいこれ」
そう言って修也たちはそれぞれ学生証を提示する。
「はい、ありがとうございます。お客様方は男性2名、女性2名のようですが、ペア割は利用しますか?」
「ペア割? 何か携帯のプランみたいなのが出てきたけど何それ?」
「簡単に言えば、男性と女性のペアで割引が適用されるというものです」
修也の質問に対し、丁寧に回答してくれるお姉さん。
「でももう学割が……」
「大丈夫ですよー。重複して割引されます」
「随分と良心的だな……」
「あ、ちなみに私は彰彦と利用するわよ」
そう言って爽香はペア割の利用を宣言する。
今までに何度も来て利用しているのだろう。手慣れている感がある。
「かしこまりましたー。そちら様はどうしますか?」
そう言ってお姉さんは詩歌の方を見た。
「えっ……わ、私……? で、でも……先輩と、私は……ただの学校での先輩と後輩の、関係で……」
しどろもどろになりながら顔を紅潮させて俯き小声で呟く詩歌。
「あ、大丈夫ですよ。要は男性と女性が1人ずつであればOKです。関係は不問です」
そんな詩歌に対し、笑顔で詳細の説明を入れてくれるお姉さん。
「あれ、そうなの? そういうのってカップル限定ってイメージだけど」
「基準が曖昧で証明が難しいですからねー。カップルの証拠を出せって言われてもどうすれば良いか分からないでしょう?」
確かに言われてみると、カップルであることの証明なんてどうすれば良いのだろうか?
仲良く2人で写っている写真でもあれば証明になるのだろうか?
(でもそれだと俺と蒼芽ちゃんは紛うことなきカップルになるな。これでもかという程写真撮ったし)
修也は、昨日蒼芽にせがまれて写真を撮りまくった事を思い出す。
結局何枚撮ったのか覚えていない。
あまりにも多かったので途中で数えるのを放棄したのだ。
「それだったらもう男女1人ずついれば良いじゃんってなりまして」
修也が考え事をしている間にもお姉さんの話は進む。
修也は思考を打ち切り、お姉さんの話に意識を向ける。
「……おおらかなのか適当なのか分からんな……」
「そこまで行くと、あえてペア割を利用しない理由が見つからないんだけど」
爽香の言う通りだ。あえてペア割を使わず本来の入場料で払う人などいないだろう。
「2人で来てもらうということに意味があるんですよー。このペア割があると、デートとか遊びに誘いやすくなるでしょ?」
「なるほど、『ペアで行けば少し安くなるから一緒に行こうよ』となる訳か」
彰彦が納得したように呟く。
つまりこのペア割は、誘う口実を作りやすくするために作られたものなのだろう。
「当園としてもお2人の親睦を深めるお手伝いができるのなら光栄という訳です」
「ほぉー……で、本音は?」
「1人より2人で来てくれた方が単純に儲かるじゃないですかー」
「ぶっちゃけたぞこの人!?」
修也のフリにしっかり乗っかって応えてくれるお姉さん。
結構ノリのいい人のようだ。
「という訳なので、ただの先輩後輩の間柄でも全然問題ないですよ」
「どういう訳だ……でもまぁそういう事ならせっかくだし利用するか」
「は、はい……せ、先輩が……嫌でないのなら……」
「かしこまりましたー。ではペア2組で4800円です」
「じゃあこれで」
「お、良かった小銭ピッタリあるな」
そう言って修也と彰彦がそれぞれ半分ずつ出した。
「えっ……!?」
「はい、ちょうどいただきました。こちら入場券になります」
入場料を受け取ったお姉さんは4枚のチケットを修也に手渡した。
「行ってらっしゃーい! 楽しんできてくださいねー!」
そう言ってお姉さんは笑顔で修也たちを見送った。
「あ、あの……アキ君、先輩……その、お金……」
お姉さんに見送られてカウンターを離れる修也と彰彦に、詩歌が慌てて声をかける。
「ん? ああ、爽香とのデートでは一旦俺が出して後で清算ってスタイルだからいつもの習慣で」
「あそこであれ以上変に手間取って後ろの人を待たせる訳にもいかなかったしな。2400円ならちょうど出せたし」
あくまでも自分たちの都合だと主張する彰彦と修也。
「あ、あの……先輩、後でちゃんとお金は、払いますから……さっきのお水のお金も……」
「別に気にしなくてもいいんだが……まぁ、変な金の貸し借りは無い方が良いよな」
先週蒼芽と出かけた時もどちらが出すかで結構もめた。
修也としては気にしなくても良いのだが、お金を出してもらう側からすれば結構気を遣うものなのだろう。
「さ、これで今日一日は好きに遊び回れるわよ」
「え、全施設使えるのか? それでこの金額ってむしろ安くね?」
ペア割と学割を併用しているとはいえ、遊園地以外にも様々なアクティビティがあるのにそれでこの値段は良心的というレベルではない。
「値段を安く抑えて何度も来てもらおうって魂胆なんでしょ。どのみち全施設を一日で回るなんて無理な話なんだし」
「ああ、そういう……」
確かに爽香の言う通り、一日で全施設を遊びつくせるかと言われたら無理だろう。
何度も来ようと思わせるなら、それなりの値段設定が必要という訳だ。
ちゃんと利益を考えていると思わせる所に修也はむしろ安心した。
その原因は、利益度外視で教育施設を運営しているどこぞの資産家にあると思われる。
「ちなみに施設内での飲食費は別途かかるぞ」
「まぁ流石にそれはどこだってそうだろ」
「はいはい、じゃあさっさと行きましょ。まずは……これよ!」
そう言って爽香が指さしたのは……
「……ジェットコースター、だな」
「そう! 遊園地と言えば外せない定番でしょ」
「確かに。しかし凄いな、日本最高速かつ最高高度って書いてるぞこれ」
修也が見たジェットコースターの看板には、『日本最高速! 最高高度! 最恐のスリルをあなたに!!』という謳い文句がでかでかと書かれていた。
「……でも、大丈夫か?」
「何がよ」
「こういうのメチャクチャ苦手そうなのが1人いるけど……」
そう言って自分の横を見る修也。
そこには……顔を真っ青にさせてガタガタ震えている詩歌の姿があった。
明らかにこの手合いの絶叫マシンは苦手そうである。
「お、おおおお姉ちゃん…………こ、ここれれにににのの乗るのののの……?」
「すっげぇ震えよう……これ、無理に乗せたら途中で心臓止まるんじゃね?」
「流石にそこまでは……でも、無理強いしないのには賛成だ」
尋常じゃなく震えている詩歌を見て、彰彦も擁護に回る。
「まぁそれもそうね……じゃあ私と彰彦で乗ってくるから、その間詩歌は土神君と別の乗り物に行ってきなさいよ」
「えっ」
「この遊園地は広いから、詩歌でも乗れそうなマイルドな乗り物だってきっとあるわよ」
「えっ……えっ……?」
「あ、そうだわ。せっかくだし午前中はそれぞれ別行動にしましょう」
「あー……悪い土神、爽香の方は俺が何とかしておくから、詩歌の事頼めるか?」
「ああ、分かったよ」
「え……えぇっ……!?」
あれよあれよと事態が変わっていくことに、詩歌の青かった顔色は一瞬で赤くなる。
「じゃあ詩歌、土神君にしっかりエスコートしてもらうのよ」
そう言って爽香は彰彦を連れてジェットコースターの行列に並び始めた。
「エスコートも何も……俺、初めてここに来たんだが……」
「あ、あのっ……先輩、ごめんなさい……」
爽香と彰彦の背中を見送りながら呟く修也に、詩歌は頭を下げて謝る。
「え? 何が?」
「ま、また私のせいで……先輩に、不自由な思いを、させてしまって……」
「いや別に、不自由だなんてことは」
「で、でも……このジェットコースターには……乗れなくなってしまいましたし……」
「あー、うん……これね……」
そう言って修也は視線を上に向ける。
スタート地点からすぐかなりの急角度でレールが上を向いており、最高点に達してからしばらくは水平に続いている。
そしてほぼ垂直落下に近い向きで地面スレスレまで急降下し、その後はレールが捻られたり波打ったりしている。
今もコースターからの絶叫に近い悲鳴が、かなり距離の開いている修也の立っている所にまでしっかりと聞こえてきた。
「……うん、これは俺も気乗りしない」
「……え?」
修也の言葉に、意外そうな顔をして頭を上げる詩歌。
「乗ろうって誘われたら乗るかもしれんが、自分から乗ろうって気にはなれんな」
「そ、そうなんです、か……?」
「遊園地は楽しむ所だろう? あえて怖い思いをする意味が分からん」
「で、ですよね……!」
修也の考えに同調するように、強く頷く詩歌。
「お姉ちゃんは……その怖い思いが楽しいって、言うんですけど……私には全く分からなくて……」
「まぁ感じ方は人それぞれだからな。姉妹だからって似るもんでもないし、似せる必要もないだろ」
「そ、そうです、ね……」
「だからさ、詩歌も楽しめるものを探しに行こう。時間の余裕はたっぷりあるからな」
「は、はいっ……!」
修也の言葉に笑顔で頷いた詩歌は、修也の横に並んで歩く。
(良かった……先輩も、絶叫系は好きじゃなかったんだ……)
詩歌は、自分のせいで修也の楽しみを減らしてしまったのではないかと思っていたのだが、その可能性はなさそうであることにほっと胸を撫で下ろした。
(ふふっ……なんか……先輩と共通点があって、嬉しい……かも)
修也の新しい一面を知れて、詩歌は少し心が弾むのであった。
(……とりあえず自責の念は消えたかな?)
一方で、表情が明るくなった詩歌を横目で見ながら修也はそう心の中で呟く。
修也は修也で、詩歌が自分のせいで修也が楽しめていないのではないか、と自分を責めてはいないか懸念していたのだ。
なのであえて『自分も絶叫系はあまり好きじゃない』と思わせることで、詩歌に『自分のせいでジェットコースターに乗れず、楽しめなかった』と思わせないように誘導したのだ。
先程自分で言った通り、遊園地は楽しむ所だ。
せっかく遊びに来たのだ。
楽しむなら一点の曇りなく楽しまないともったいない。
(……まぁ、普通に気乗りしなかったってのもあるっちゃあるけどな……)
修也はちらりと後ろを見る。
コースターは今まさに落ちようとしているところだった。
再び聞こえてきた絶叫に近い悲鳴が修也と詩歌の耳に飛び込んでくる。
「……乗らなくて正解だな、ありゃ」
「……はい……」
2人は未だ響く悲鳴を背に、別の乗り物を探しに行くのであった。
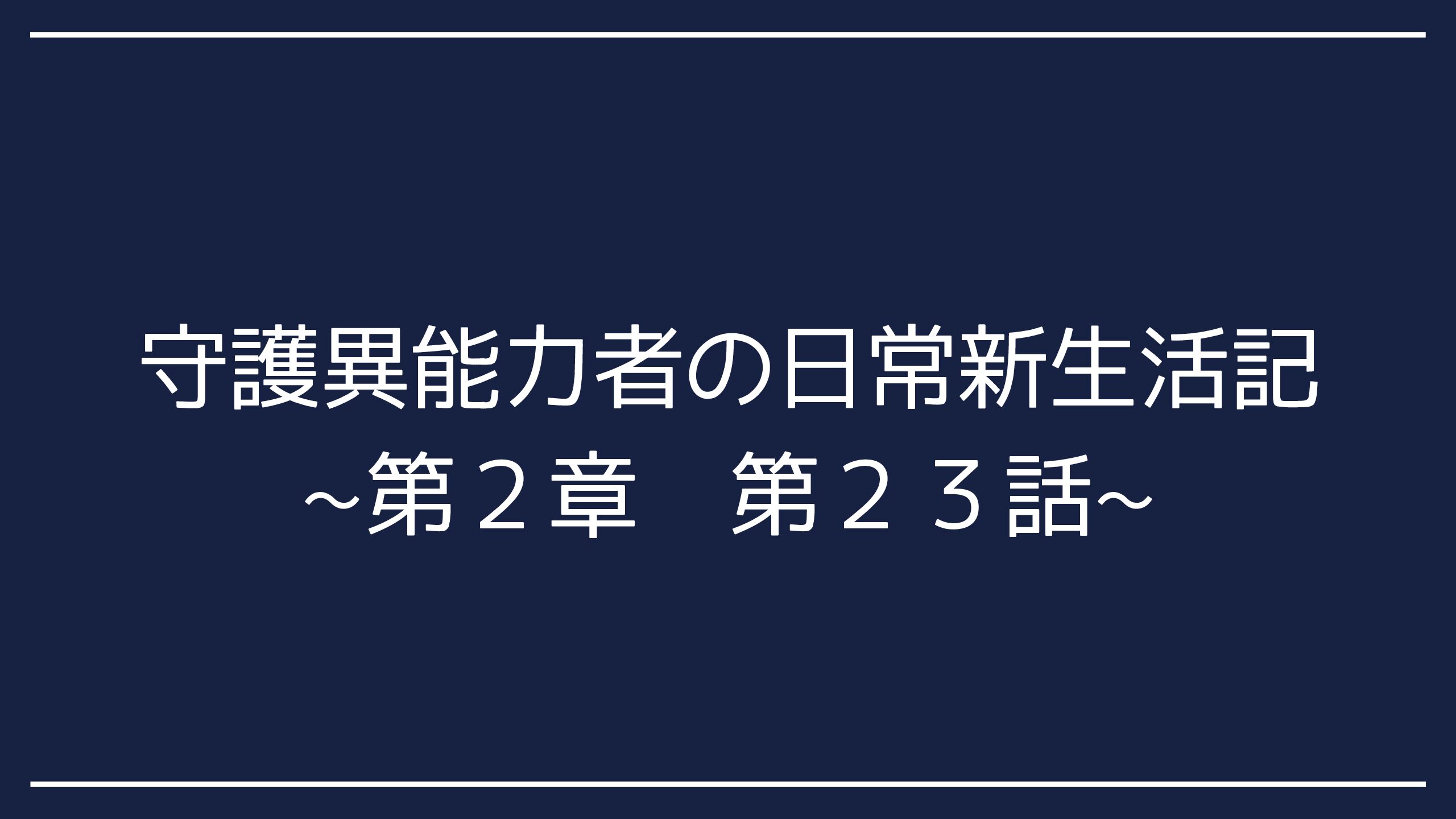

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]