「ここから電車で3駅だったっけ? これから行く場所は」
改札を通りホームで電車待ちをしている間に修也はこれから行く場所について確認する。
「ああ。時間にして大体10分強ってところだ」
「アクセスが楽なのは良いんだけど、その分人が多くて混雑するのが難点ね」
彰彦と爽香が修也の問いに答えてくれる。
「まぁそんな施設があればそうなるのも無理ないか……あれ、でも俺がこっちに来た時はそんなに混んでなかったけど」
修也は今の町に引っ越してきた時のことを思い出すが、そこまで言うほど混雑はしていなかったはずだ。
「土神が来たのっていつの話だ?」
「先週の木曜日」
「平日じゃない。だったら混んでないのは当り前よ」
「ああ、それもそうか」
一般的に遊戯施設を利用する人でごった返すのは週末だ。
平日の、しかも昼間から利用する人はそうはいないだろう。
「あ、でも今日は土曜だから……」
「……10分強の辛抱だ」
「やっぱり混むのか」
「詩歌、あなたは壁際か何か掴まれるもののそばに立っておくのよ?」
「う、うん……」
爽香の言葉に不安そうな顔で頷く詩歌。
「あぁそうか。詩歌の身長じゃつり革だとアレか」
「え、えっと……無理ではないんですけど……ずっと腕を上げっぱなしになるので……」
「確かに10分強それはダルいな」
「かと言って掴まるものが無いと、それはそれで揺れた時に危ないしな」
「何だったら土神君に掴まってたら?」
「え……えぇっ!? そ、そそそそそれは……」
爽香の提案に、顔を赤くさせて驚く詩歌。
「いやそれ意味ねぇだろ。固定されてないから電車が揺れたら俺も揺れるぞ」
「あら、土神君なら揺れてもバランス崩さず立ってられるんじゃない?」
「何を根拠に言ってんだ」
「ガタイの良い男と真っ向勝負でやりあって勝てるんでしょ?」
「全く関係ねぇー……」
「何の根拠にもなってねぇー……」
爽香の言い分に呆れ顔の修也と彰彦。
「詩歌、普通に危ないからつり革が無理なら手すりを持てば良い」
「あ……うん、そうだね……」
詩歌は彰彦の言葉に頷く。
「ああでも懐かしいな。小学生くらいの時はつり革も手すりも持たずどれだけ足を動かさず立ってられるかってやったっけ」
「お、土神もか。俺も一時期ハマって独自で研究したりしたもんだ」
「進行方向に対して斜めに足を置くのは基本だったか?」
「あーそうそう! 垂直でも平行でもない、斜めが一番安定する気がしたよな!」
「どこでも考えることは一緒なんだなぁ」
そんな昔話で話題に花を咲かせているうちに電車がやってきた。
電車の中は座席こそ埋まっているものの、そこまで混雑しているわけではなさそうだ。
「じゃ、電車も来たことだし行きましょうか」
爽香の言葉を合図に、修也たちはやってきた電車に乗り込むのであった。
守護異能力者の日常新生活記
~第2章 第22話~
「あ、詩歌、あそこ空いてるぞ」
「あ、うん」
彰彦が指さしたのはドアのすぐ側で、なおかつ座席の端の場所だ。
そこなら手すりも程よい高さにあるし、何より壁がある。
しかも乗客が出入りする際、流れに巻き込まれないで済む。
彰彦に促され、詩歌は立ち位置を確保する。
「あとはどうとでもなるだろうけど、土神、一応詩歌のカバーを頼む」
「ああ、頼まれた」
「……え?」
彰彦の言葉の意図をくみ取った修也はちょうど詩歌の正面に立つ。
「あ、あの……せ、先輩……?」
「ああ、これは人混み対策だ」
「人混み……?」
「まぁどこにでも言える話なんだが、混雑してくるとあっちこっちから押されて圧縮されるんだよな」
「あ、はい……確かに……」
詩歌は実際に満員電車を体験したことは無いが、ニュースなどで見たことはある。
見ただけでもう非常に苦しそうだと思ったのを覚えている。
「車内のど真ん中だったら四方八方から押されて大変なことになるけど、幸いそこは隅だからな。押される方向は限られる」
今詩歌が立っている場所は、背中が壁で横は片方が座席だ。
そちらから押されることはまず無いので気にする必要がなくなる。
「で、その限られた方向を俺がカバーしておけば詩歌が押しつぶされることはなくなるってわけだ」
「で……でも、それだと先輩が……」
「大丈夫大丈夫。そんな朝の通勤電車とかどっか海外の乗車率500%超とかじゃなければたかが知れてるって」
「ご、500……ですか……!? え……通勤電車だと……凄く混んでて……ぎゅうぎゅう詰めになっても、200とかだったと思うんですけど……」
「新幹線だと120でも多い方だな。盆正月にやるニュースでよく聞くよな」
「あの……どうやって乗ってるんですか、それ……?」
あまりの数の大きさに衝撃を受けた詩歌は当然誰もが浮かぶであろう疑問を口にする。
「つま先だけ乗って身を乗り出したり屋根に乗ったりしてるらしい」
「あ、危なくないですか、それ……?」
「うん、危ない。だから絶対マネしないようにな」
「し、しませんよ……というか、できません……」
そんな話をしているうちにドアが閉まり、電車が動き出した。
電車内は混んではいるが、周りから押されるほどではない。
ふと、詩歌はそこであることに気が付いた。
(あれ、そう言えば……今のこの立ち位置……先輩が凄く近い……!)
詩歌が電車の隅に立ち、修也がそれを人混みから守るように立っているので、今までにないくらい距離が近いのだ。
基本的に詩歌は人見知りが強く、パーソナルスペースもかなり大きい。
家族と彰彦はまだマシな方ではあるが、それでも近くにいられると落ち着かない。
それが修也相手となると尚更である。
しかし人混みから守ってくれている修也に対して『もう少し離れてください』とは、心情的にも物理的にも、そして性格的にも言えない。
(ど、どどどどうしよう……! わ、私、汗臭くないよね……!? 先輩に不快な思いさせてないよね……!?)
意識しだすと急に色々と気になってあたふたしだす詩歌。
かなり挙動が怪しい。
「……詩歌、どうした? かなり挙動が怪しいけど」
そしてそれに気づいた修也に指摘される。
「えっ!? い、いいいいいえ、ななななんでも、ないです……!」
「……まぁ、詩歌がそう言うなら……」
どう見ても何でもないことはなさそうなのだが、本人がそう言っている以上深く踏み込むのも気が引ける。
もしかしたらこの混雑に紛れて不埒なことを考える輩でもいるのかと勘繰ったが、位置的にそれはあり得ない。
(単に混雑してて窮屈なだけかな……)
そう修也は結論付けた。
だとすると出来ることは何もない。
目的の駅に着くまで辛抱してもらうしかない。
「目的の駅まで3駅あるんだったな。頑張れ詩歌。もう少しの辛抱だ」
「は、はいぃ……」
修也の言葉に小さく頷き、隅で縮こまる詩歌。
と、ここで電車の速度が落ちてきた。
どうやら1つ目の駅に近づいてきたようだ。
「……あれ?」
その時修也は1つ気になることができた。
「……ど、どうしたんですか、先輩……?」
「なぁ詩歌、知ってたらで良いんで教えてほしいんだが……」
「は、はい……私で分かることなら……」
「普段は次の駅で降りる客と乗る客ってどっちが多い?」
「え? えっと…………すみません、私……あまり電車に乗らないので……」
修也の問いに答えられず、申し訳なさそうに俯く詩歌。
「ああいや、分からないなら良いんだ。気にしなくて良い」
「は、はい……」
「じゃあちょっと聞き方を変えよう。今この電車がこんなに混んでるのは、大半がアミューズメントパーク目当てと見て良いんだよな?」
「えっと……多分そうだと思います……」
平日はそんなに混んでいない電車が週末はそこそこ混んでいる。
ということは、全部ではないだろうが遊びに行く人が大半と見て良い。
「で、次の駅もその次の駅もそんな人がいるだろうな」
「まぁ……週末ですから……」
「と言うことは、ここからさらに乗客が増える可能性がある。というかほぼ間違いない」
「え……と、いうことは……」
ここで詩歌も修也が気になっていることの正体が分かった。
それは……
「ああ、きっとさらに混むぞ」
「!!」
この電車のこれからの混み具合だ。
修也の言葉と同時に電車が止まり、ドアが開く。
そしてホームで待っていた客が乗り込んできた。
降りる客はいなくはなかったが、乗る客に比べたら微々たるものである。
当然先程よりも電車内は混雑した状態になった。
「っと……詩歌、大丈夫か?」
人混みの圧を背中に受けながら、修也は詩歌の様子を伺う。
(せ、せせせせ先輩が、さっきよりも……ち、近いぃ~~~!!?)
その詩歌は内心かなり穏やかではない。
修也がガードしてくれているおかげで詩歌が押されることは無かった。
しかし、やはりどうしても距離は詰まる。
さっきまでは体一つ分くらいの隙間はあったのだが、今は鼻先に修也がいる。
その事に詩歌の動悸と呼吸は激しくなり、緊張で目の前がクラクラしてきた。
(わ、私の息が……先輩にかかっちゃう……! き、気持ち悪いって思われないかな……?)
もう詩歌は圧迫感と緊張で意識が遠くなりかけていた。
「ここでこれだけ混むってなら次の駅はどうなるんだろうな」
「え」
だがこの修也の言葉で一瞬我に返る。
(そ、そう言えば……まだもう1駅あるの忘れてた……!)
次の駅でも恐らく乗ってくる客はいるだろう。
今でさえ鼻が触れそうな距離なのだ。
これがさらに詰まるとなると……
(お、お願い……! これ以上お客さん増えないで……!)
詩歌は必死に懇願するが、その願いは叶わず次の駅でも客は乗り込んできた。
ちなみに降りる客はいなかった。
その結果……
(~~~~~~!!)
距離はさらに詰まり、詩歌は鼻先どころか体の前部分全てが修也に押されている状態になった。
「詩歌? 大丈夫か? 息できてるか?」
「ふぁ……ふぁい……」
修也の問いかけに、心の半分がどこか行ったような状態で返事をする詩歌。
「あと1駅だからな。もうちょっとだ」
「ふぁい……」
「出口は……あ、良かったこっち側だ。着いたらすぐ降りられるな」
車内の液晶掲示板の表示で出口を確認した修也がそう呟く。
が、詩歌の耳にはほとんど入っていない。
(わ、私……せ、先輩の腕の中にいる……密着しちゃってる……! ご、ごめんなさい先輩、わざとじゃないんです……!!)
修也と密着してしまっていることに心の中で必死に謝る詩歌。
自分でも言っている通り不可抗力なので別に謝るようなことではないのだが、パニック状態の詩歌は気づかない。
今自分の顔は今まで見たことが無いくらい真っ赤になっているだろう。
それに密着してることで心臓の鼓動が聞こえてしまうかもしれない。
そんな思考が詩歌の頭の中でぐるぐる回って加速していく。
(は、早く駅に着いてぇ~~…………!!)
もう詩歌には、早く目的地である次の駅に一刻も早く着くことを願うことしかできない。
しかしそういう時の時間は物凄く長く感じるものである。
3分弱程度であるこの時間が詩歌には何十倍にも長く感じられるのであった。
「ふぅー……相変わらずの混み具合だったわね」
目的の駅に着き、電車を降りた爽香は体を軽く伸ばして解す。
「全くだよな。電車の本数を増やすとか違う交通手段を用意するかしてほしいもんだ」
彰彦も肩を回しながら大きく息を吐く。
「いっそ歩いて行くってのはどうだ?」
「土神……それを普通にやれるのは霧生みたいなやつくらいだぞ」
修也の提案に呆れ顔の彰彦が答える。
「でもまぁ、あの満員電車に乗り込むことを考えたらそう言う選択肢を取りたくなるのも無理ないわね」
「だろ?」
「ただその場合は行くだけで疲れるわよ」
「……それもそうか」
修也もそこそこ体力はある方ではあるが、3駅分歩いてそこからさらに遊園地を歩き回れる気はしない。
2キロを全力疾走してさらにそこから筋トレまで余裕でこなす戒くらいの体力が無いとそんなことを平然とはできないだろう。
「…………で、そろそろ大丈夫か、詩歌?」
「………………きゅう……」
彰彦が詩歌に声をかけるが、詩歌はホーム備え付けのベンチに座って目を回したままである。
「詩歌にあの人混みはきつかったかー……」
「2駅目まではまだ大丈夫そうだったんだけどなぁ」
「最後の混み具合ハンパなかったもんな」
「私でもちょっとキツかったわよ」
「…………」
詩歌が目を回しているのは人混み酔いだけではないのだが、それに気づいている人はいない。
知っているのは本人のみである。
「じゃあ俺ちょっと水買ってくるよ」
修也はそう言って彰彦たちから離れ、売店か自販機が無いか探す。
程なくして自販機が見つかったので修也はペットボトルの水を1本買い、元いた所に戻る。
「ほれ詩歌、水だ。飲めるか?」
そう言って詩歌にペットボトルを差しだす修也。
電車の外に出て風に当たったからか詩歌は体調を少し持ち直したようで、差し出されたペットボトルを受け取る。
「あ……は、はい……すみません、先輩……お手数おかけしてしまって……あとでちゃんとお金は返しますから……」
「良いって、気にすんな」
受け取ったペットボトルのふたを開け、詩歌は水を口の中に少しの間含ませてから飲む。
それを何回か繰り返しているうちに、詩歌の顔色は大分良くなってきた。
「詩歌、そろそろ立てそうか?」
「う、うん……大丈夫だと、思う……」
「もしきつそうだったら無理せず言うのよ? あ、そうだ。何だったら土神君に支えてもらったら? こう、土神君の腕に掴まって」
「え……えぇっ!?」
爽香の提案に、さっきまで青かった詩歌の顔色が逆に赤くなる。
「だ、大丈夫だよ……そんな、先輩にご迷惑をかけるわけには……」
「別にそれを迷惑だとは思わんけど、ホントに辛かったら言えよ? ちゃんと休憩するから」
「あ……は、はい……」
修也にそう言われ、詩歌は赤い顔のまま俯いて頷くのであった。
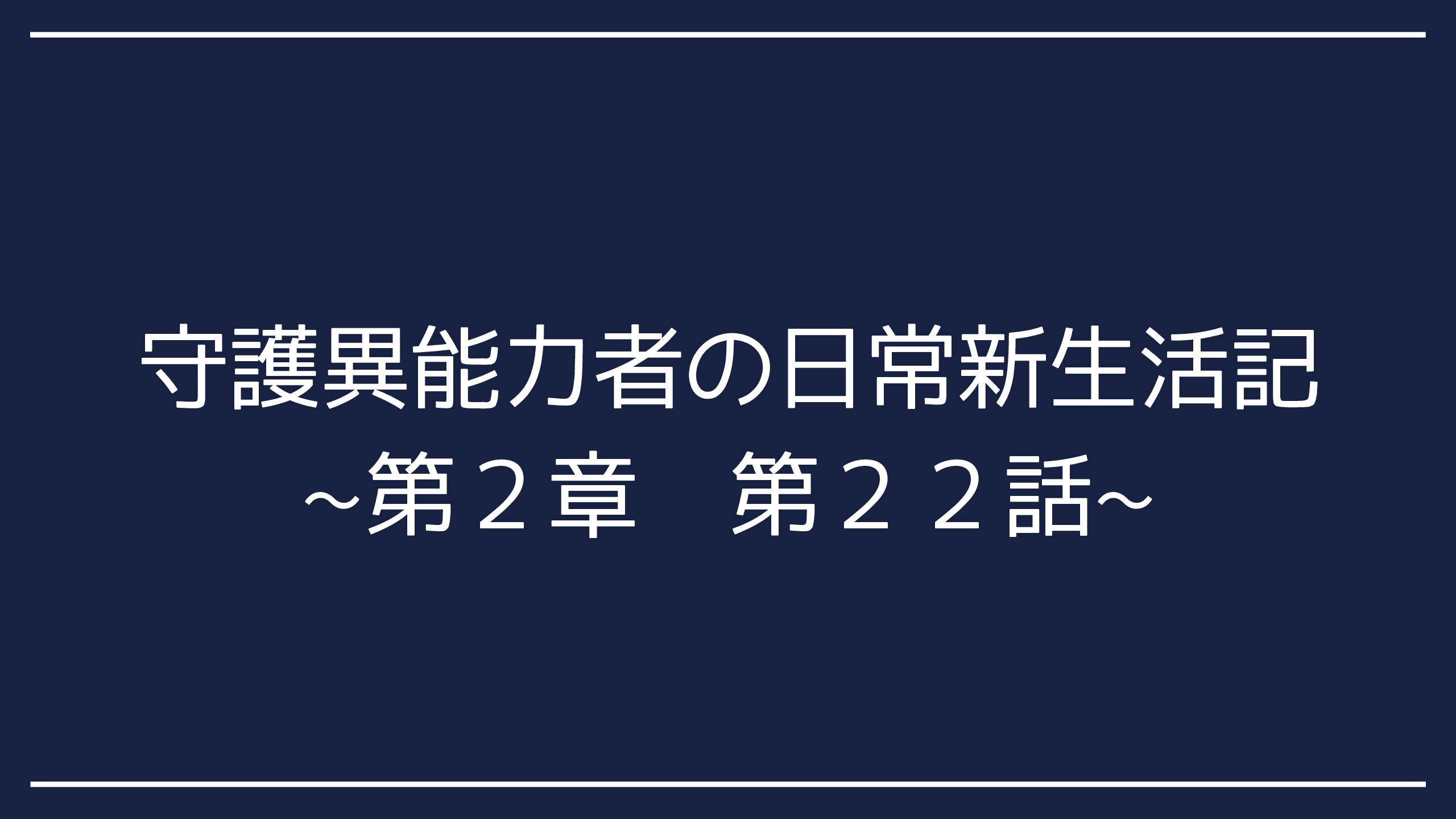

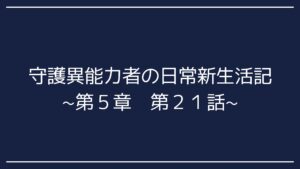
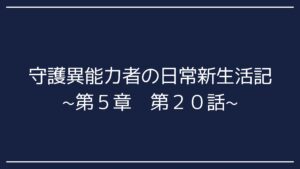
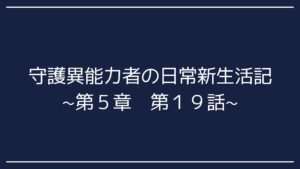
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]