「お話の途中だったのにすみません、猪瀬さん。友達の姿が見えたので挨拶しておこうと思いまして」
そう言って猪瀬と呼ばれた男子生徒に軽く謝る華穂。
(ん……?)
修也は今の華穂の言動に違和感を覚えた。
(何で華穂先輩、敬語を使ってるんだ……?)
華穂が敬語を使っていたからだ。
華穂は敬語を使うのも使われるのも嫌がる。
修也が華穂のことを先輩だと気づいて言葉遣いを直そうとした瞬間にストップをかけたくらいだ。
流石に教師などの目上の人に対しては使うだろうが、目の前にいる猪瀬は制服を着ているので生徒だろう。
華穂は3年生だ。なので先輩という線も無い。
留年生の可能性も僅かながらにあるかもしれないが、華穂がそんな理由で敬語を使うとは思えない。
なのに華穂は猪瀬に対して敬語を使っている。
(それに今の先輩の口調、相手を敬うというより……)
敬語は場合によっては他人行儀に捉えられることがある。
修也には今の華穂の言葉に拒否の意思が見えた気がしたのだ。
表情も無機質で、できるだけ関わりたくないことが伺える。
「ほーぅ……友達、ねぇ……?」
そう言って猪瀬は修也を嘗め回すように見る。
(……うわ、不快感ハンパねぇ)
それだけで修也の背筋に悪寒が走った。
「華穂さん、顔が広いのはあなたの美点ですが付き合う人間は選んだ方が良い。あなたのような方にこんな下級庶民は似合わない」
「……は? 下級とか何言っちゃってんのこの人」
「やれやれ、自分が身分の底辺にいるという自覚が無いとは……これだから庶民と関わるのは嫌だ」
「やめてください猪瀬さん。私の大事な友達にこれ以上失礼な発言をするのは看過できません」
そう言う華穂の言葉には明らかに怒りが混じっている。
「…………ふん、まあ良い、ここは華穂さんに免じて引いてあげよう。寛大な上級国民である僕に感謝したまえ」
「……上級だのなんだのってネタじゃなくて言ってる奴初めて見たよ。この日本で身分の差なんてある訳無いのに」
「そうだよねー。まともな感性と知性があるなら自分が上級国民だとか恥ずかしくてとても言えないよ」
修也と話す時だけは無機質な表情をやめて微笑む華穂。
敬語も無く言葉遣いも柔らかい。
「っ! この、庶民風情が……!」
修也に馬鹿にされたと感じたのだろう。猪瀬が修也を睨む。
……が、つい先日狂気に染め上げられた憤怒の表情をした人間を間近で見た修也としては、そんなものチワワに唸られている程度にしか感じない。
つまり全く怖くない。
本物のチワワのような可愛さは微塵も無いのでただひたすらにウザくて不快なだけだ。
「…………ふっ、所詮下級庶民には何を言っても無駄か」
威嚇(?)が全く通用しなかったのを誤魔化すかのように猪瀬はくるりと背を向ける。
「それでは華穂さん、先程の話、是非前向きに検討をお願いいたします」
「お断りします。あのような話、受けるつもりは毛頭ありません」
猪瀬の言葉に対してきっぱり拒絶の意思を示す華穂。
「……ククク、華穂さん……あなたもいずれ分かります。この世界の真理と僕の魅力に……」
しかし猪瀬は全く意に介さず、含み笑いをしながらその場を去っていった。
守護異能力者の日常新生活記
~第3章 第6話~
「……いや、何アレ?」
猪瀬が廊下を曲がり見えなくなってから修也はそう呟く。
「ゴメンね土神くん。でも私が邪魔してほしいって言った理由が分かったんじゃないかな」
「ああ……うん、確かにアレと1対1で話するのは辛いわ。精神力がゴリゴリ削れる」
猪瀬のことを『アイツ』とすら呼ばずに『アレ』呼ばわりする修也。
どれだけ不快だったかがそのあたりから窺い知れる。
「でしょ? だからさ土神くん、昼休みが終わるまでちょっと気分転換に何かどうでも良い話しない?」
「どうでも良い話?」
「うん、実生活において何の役にも立たないどうでも良い話。そういう話で笑えたら気分も晴れるかなってね」
「しかしいきなりそう言われてもな……」
華穂に言われて修也は考え込む。
「……あ」
しかし意外にも割とあっさり思いついた。
「あ、何か良い話思いついた?」
「なぁ華穂先輩。先輩はきのことたけのこならどっちが好きだ?」
さっき塔次を発端とし、白峰さんと黒沢さんが激しい(?)論戦を繰り広げてたきのこたけのこ論争を修也は思い出した。
修也的にどうでも良い話だと切り捨てていたのだが、華穂からまさに『どうでも良い話』を要求された今ならちょうどいい。
なのでその話を華穂に振ってみる。
「あ、もしかしてあのお菓子の話?」
「そうそう。今朝うちのクラスで壮絶な論戦が繰り広げられててな」
「……やっぱり土神くんのクラスはユニークだねぇ。楽しそうで羨ましいよ」
「第三者として傍観する分には良いんだけどな……何故か毎回変に絡まれるから堪ったもんじゃない」
「で、今朝のその論戦は決着がついたの?」
華穂が興味深そうな顔で先を促してくる。
「いや、いつまで経っても平行線で決着がつかず、最終的に人気投票で決めることにしたらしい」
「あー、やっぱりそう簡単には結論は出ないかー」
「第三勢力を投入しようとか言い出す奴もいてもう訳が分からん」
「あ、第三勢力と言えば、実は昔すぎのこっていう第三勢力がいたんだよ」
「え、マジ!?」
華穂からもたらされた情報に修也は驚く。
「ただ、別のお菓子と被ってたせいかすぐ消えてなくなっちゃったみたいだよ」
「そうだったのか……それは知らなかったな」
「また第三勢力が出てきたらそれはそれで面白そうだね」
「……でも、めんたいこは無いな、うん」
「え? めんたいこ? 何で急にめんたいこ?」
急に全く関係無い単語が出てきたことに首を傾げる華穂。
「……いや、第三勢力に何かいいアイデアは無いかと聞かれてさ」
「うんうん。それで?」
「それで俺、適当に『めんたいこの港』って答えたんだよ」
「…………ぷっ、あっはははははは! 良いね土神くん! 面白いよその発想!!」
修也のセリフに大笑いする華穂。
「ふぅー、笑った笑った! おかげで憂鬱な気分が吹き飛んだよ!」
そう言う華穂の表情は実に晴れ晴れとしている。
「そうか? それなら良かった」
「あっ! そうだ土神くん、話は変わるけど携帯持ってる? 持ってるなら連絡先交換しておこうよ」
華穂がスカートのポケットからスマホを取り出しながらそう提案する。
「え? 持ってるけど……良いのか? 俺の連絡先を入れちゃって」
「ん? どういうこと?」
修也の言葉の真意が分からず首を傾げる華穂。
「こうやって話してると時々忘れそうになるけど、華穂先輩っていいとこのお嬢様だろ?」
「良いよ? 別に時々じゃなくて常に忘れてても」
「良いのか!?」
「私、あんまりこのお嬢様って肩書好きじゃないんだよねぇ。何か身の程にあってないというか名前負けしてるというか」
「あー、それは何となく分かる。俺も一部でヒーローだとかアイドルだとか現人神とか言われてるらしいし」
「私より凄い肩書持ってるね土神くん! 神様になっちゃってるよ!?」
修也の言葉に目を丸くして驚く華穂。
「一体何したの? そこまで言われるって相当だよ?」
「先日この学校に不法侵入してきた不審者をぶっ飛ばした」
「あ、それ土神くんだったんだ!」
「……まぁそれはどうでも良い」
話が脱線しつつあることと、あまり深く掘り下げてうっかり『力』のことを話してしまうことを恐れて修也は話をぶった切る。
「えぇー、もっと詳しく聞きたいなー」
「今はその話よりも連絡先交換の話だろ?」
「ああそうだったね。土神くんの連絡先を入れても良いかどうかってどういうこと?」
「いやぁ、お嬢様って監視が厳しくて、毎晩スマホを検閲されて男の連絡先が入っていようものなら大騒ぎになって相手の素性を徹底的に調べ上げて少しでも不審な点があれば闇に葬って……」
「ストップストップ! お嬢様に対する考えが偏りすぎ!」
修也の言葉を強引に割って入って止める華穂。
「超が付くほどの箱入りお嬢様でもやらないよそんなの」
「そうなの? 検閲くらいはありそうな気がするけど」
「それはお嬢様じゃなくても年頃の女の子がいる家庭だったら程度の差はあれどあるんじゃないかな?」
「流石に闇に葬るってのは偏見が過ぎたか……」
「とにかく、うちではそういうことは一切無いから安心して良いよ」
そう言って華穂は自分の連絡先が表示されたスマホの画面を修也に見せる。
「まぁそういうことなら……」
修也はそう呟きながら自分のスマホに華穂の連絡先を入力する。
そうしているうちに午後の授業開始5分前の予鈴が辺りに響き渡る。
「それじゃあまた何かあったら連絡するね!」
「ああ」
「何も無くても連絡するね」
「無くても連絡するのか?」
「ほら、今日みたいに雑談とかしたいじゃない? 土神くんの話面白いし」
「まぁ……程々に頼む」
「じゃ、まったねー!」
そう言って華穂は自分の教室に戻っていった。
修也も自分の教室に戻るために足を進める。
「……本当にお嬢様っぽくない人だなぁ……」
廊下を早歩きで進みながら修也は呟く。
華穂からはやはり身なりや立ち振る舞いから育ちの良さを感じ取ることはできる。
しかし言動がちっともお嬢様っぽくないのだ。
ただ別にそれが悪いという訳ではなく、気後れせずに済むので修也としてはむしろ好印象だ。
「そう言えば先輩、アレと何の話をしてたんだろ?」
つい聞きそびれてしまったが、華穂が猪瀬に何か言われていた。
何を言われていたのかは分からないが、華穂はきっぱりと断っていたあたりどうせロクなものではないだろう。
「それはそれとして……また連絡先が増えたな」
これ以上猪瀬のことで思考にリソースを割きたくない修也は考えを切り替えて自分のスマホの連絡帳を確認する。
そこにはさっきまでは無かった『姫本華穂』の名前が追加されていた。
この町に引っ越ししてくるまでは親以外の連絡先が無かった修也にとってこれは快挙である。
「……にしても女の子の連絡先多いな……」
見返してみると、連絡先に登録されているのは殆ど女の子だ。
男は彰彦しかいない。
「……こ、これはこれで由々しき事態だぞ……」
スマホの画面を見ながら修也は内心冷や汗をかく。
連絡帳に女の子の連絡先ばかり登録されているとか、女誑しだとか遊び人と取られかねない。
別に誰かに見せるわけではないので気にする必要もなさそうではあるが、修也の心境的には良しとは出来ないらしい。
かと言って良い解決策は浮かばない。
修也は引っ越す前は親以外誰とも連絡先を交換しておらず、引っ越してきてからも自分から交換しにいったことは無い。
というのも、どのタイミングで連絡先を聞けばいいのか分からないのだ。
そのあたりで実は詩歌と似通っている修也であった。
「……まぁ、なるようになるだろ、うん。一応男の知り合いだってできたわけだし……」
そう言う修也の頭に浮かび上がっているのは戎と塔次だ。
しかし……
「氷室はともかくとして……霧生、アイツスマホなんて扱えるのか?」
何気に失礼な発言をする修也。
と、そこに……
「……ん? 何だろ」
修也のスマホにメッセージの着信を知らせる通知が入った。
送信元は見たこともないアドレスだ。
「……? 業者からのメールか? 今までそんなの無かったけどな……」
気になった修也はメッセージを開いてみる。
『氷室だ。先程のきのこたけのこ論争での第三勢力のアイデアでは世話になった。こうやって知り合えたのも何かの縁だ。俺の連絡先を登録しておくが良い』
メッセージにはそんな文章と末尾に数字の羅列が記載されていた。
恐らく電話番号だろう。
「え…………なんでアイツ、俺の連絡先知ってる訳?」
表示されたメッセージを唖然とした表情で見つめる修也。
当然だが修也からは連絡先を教えてはいない。
どうやって塔次は修也の連絡先を把握したのだろうか?
「……仁敷に聞いたんだろうな。うん、それ以外方法が無い」
修也の連絡先を知っているのはクラスでは彰彦しかいない。
ならば彰彦に聞いて連絡を取ったと考えるのが自然である。
そうこうしているうちに自分の教室まで戻ってきた。
「よう土神、遅かったな」
自分の席に座ると、前の席の彰彦が話しかけてきた。
「まあ色々あって……ところで仁敷、氷室に俺の連絡先を教えたか?」
「え? いや、教えてないけど?」
修也の問いに対して彰彦は首を横に振る。
「え……じゃあ氷室はどうやって俺の連絡先を……?」
彰彦が教えてないとなると、どうやって塔次が修也の連絡先を入手したのか本気で分からなくなる。
「あー……氷室なら十分あり得る」
「ええ、氷室君なら何やってもおかしくないわ」
訳が分からなくなってきた修也とは対照的に、彰彦と横で聞いていた爽香は納得顔だ。
「……もしかして氷室もイロモノって言ったのは……」
「そう、こういう普通じゃあり得ないようなことをしれっとやってのけるのが氷室という奴なんだ」
「何をやっても『氷室君だから』で納得できてしまうのよ」
「えぇ……なんだそれ……」
修也は呆れながら塔次の座っている席に視線を送る。
次の授業の準備を終えて待機していた塔次だが、修也の視線に気づくと横目で少し修也の方を見ながら僅かに口角を上げて笑った。
「何者だよアイツ……」
「あっ、そうだ土神君。連絡先で思い出したけどなんだかんだで私のアドレス登録してないでしょ? 教えるから登録しといてね」
そう言ってスマホの画面に自分の連絡先を表示する爽香。
「そう言えばそうだったな……」
次の授業の開始が迫っているので手早く爽香の連絡先を登録する修也。
順調に連絡先は増えていくのは喜ばしいが、男女比の偏りはあまり変わっていない。
その事に複雑な表情を浮かべる修也であった。


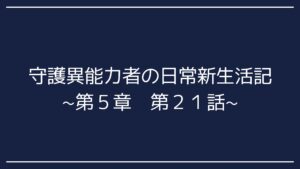
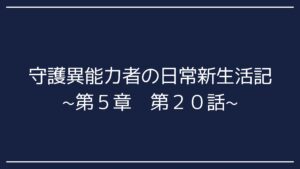
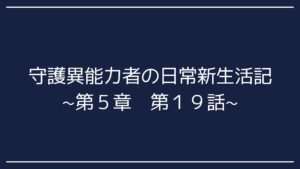
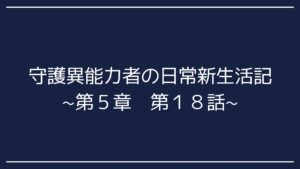
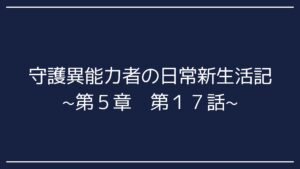
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 次の話へ […]